擦り切れてなくなりそうなわずかな望み ― 2018/06/15 01:57:44
マグダ・オランデール=ラフォン著
高橋啓 訳
みすず書房(2013年)
映画館で『サラの鍵』という映画を観た。数年前の映画だが、名画リバイバル企画で1週間だけ上映された。この機会逃すまじ、の思いだった。観てよかった。満足した。
映画が評判になった前かあとかもう憶えてなくてわからないが、原作の小説は翻訳されて単行本になっていた。けっこうな長さの本だったのですぐには手が出なかったが、何年かのち、たまたま入った古書店でリーズナブルな価格になっているのを見て買ったのだった。ところが、はっきりいうが、小説はいまひとつだった。題材、素材の求めかたは素晴しく、物語の展開も申し分ないのに、表現がくどい箇所、余計な描写が多くて、げんなりさせられる。言いたいことは山ほどあって全部盛り込みたいのはわかるが、ところどころで、というか全編にわたってそのくどさがひっかかり、かえって焦点をぼやけさせてしまっている。こいつのこのセリフはなくてもよかろうに、とか、そこまで細かく言い尽くさなくてもわかるよ、とか、つい小姑みたいに小言を言いたくなる。と、いうこともあって、これが原作なら映画は少々鼻につくかも、と思われたのだが、さすがは映画だ。言葉でくどくどくどくどグダグダグダグダゆーてたところを一瞬のシーンで語ってしまう。名優の名演で示唆する。風景や音楽でにじませる。もうその削ぎ落としかたといったら素晴しいことこのうえなかった。主演女優は好きではないタイプだが、原作には合っていると思われたので、これでいいのだった。
『サラの鍵』は、ヴィシー政権下のフランスで、パリから強制連行されアウシュヴィッツ収容所へ送られたユダヤ人の悲劇を題材にした小説である。ユダヤ人たちは「ユダヤ人」と書いたワッペンを服に縫いつけさせられ、男性は強制労働に駆り出されていた。あるとき一斉に検挙され、ひとところに収容され、やがて順次収容所に送られる。パリで起こったこの強制収容は、調べによるとナチスから命令されていたわけでなく、頃合いかと考えてフランス側が「忖度」して行ったといわれている。いずれにしろ、フランス史の大きな汚点であるとされ、長年触れられずにいたのだが、シラク政権下でこの行為にかんする謝罪声明が出された。
つまりホロコーストはドイツのナチス政権だけの犯罪ではない。当時ヨーロッパ全体がユダヤ人を排斥しようとしていた。他国は、態度を明快にしたドイツに、これ幸いと便乗したのだ。
ユダヤ人たちはあらゆる場所で被害に遭い、生き残った人々も、気の遠くなるような辛酸をなめながら這いつくばって生きてきた。自分の前半生につけられた烙印を隠し通すひともいれば、積極的に訴えるひともいた。
マグダ・オランデール=ラフォン(Magda Hollander-Lafon)は、16歳の時に故郷のハンガリーからアウシュヴィッツに強制連行された。その場で家族とは引き離され、家族はすぐガス室へ送られたが、マグダは生き残った。ほかの子どもたちとともに、屈辱的な生活を強いられながら、奇跡のように、すんでのところで機転をきかせ、生き残る方向へのあたりくじをひいたのだった。保護された先で教育を受け、教養を身につけた彼女は、年をとってから体験を書き綴り、周囲を驚かせた。そんな過酷な人生を送ってきた人だとは誰も思わなかったという。マグダの収容所生活を綴ったくだりは、『サラの鍵』のサラの経験と重なる。マグダの詩や文の行間に、映画『サラの鍵』や、『サウルの息子』で観て脳裏に焼きついていた映像が、幾度も浮かんだ。
痛ましい、凄まじい、というような言葉では表現できない。想像を絶する。
原題は:
Quatre petits bouts de pain
Des ténèbres à la joie
(四つの小さなパン切れ
暗闇から喜びへ)
収容所で、息も絶えだえになっているひとりの女性が、マグダに四つの小さなパン切れを与えてくれた。からからに乾いた、硬い小さな塊だった。マグダは、そのかびたうえにかちかちの、しかしあまりに貴重な、パン切れを食べた。パン切れは、物理的に空腹をまぎらしただけでなく、望みを捨ててはいけないことを教えてくれた。収容所での生活では、絶望しかない環境ながら、ごくごくたまに、人心に触れることがあった。それは、真っ暗闇に差すひとすじの光のような、かけがえのない、しかしすぐに消え入りそうな希望だった。マグダは、そんな擦り切れてなくなりそうなわずかな望みをもちつづけ、生き延びることができたのだった。
本書は2部構成になっている。
前半はマグダが収容所での経験を詩のように綴った「時のみちすじ」。これは1977年に一度まとめられ、 フランスで出版されたという。その反響はさざ波のように徐々にひろがり、マグダは、自分の体験を後世に語り継ぐことの重要性を痛感する。そして中高生たちと対話をするようになり、その内容をまとめたものが、後半の「闇から喜びへ」である。
よく書いてくださったと思う。
書き残すことはとても重要だ。
辛苦の記憶を書き綴ることは自分で自分を拷問するに等しいこともある。
しかし、苦しんだ人には、書いてくださいと言いたい。
(自分も、書いていこうと思っている)
(いや、たいした苦しみは経験していないのだけれども)
ナチスの蛮行はどのような理由を並べようと正当化できない。そのことは、現代人である私たちには自明のことだ。しかし、現代人である私たちは、いったい、ナチスの蛮行を、どの程度知っているだろうか?
戦後、多くの証言が掘り起こされたとはいえ、それは断片的な事柄のつぎはぎをもとにした「想像」である。その「想像」はかなりの精度でほんとうにあったことを再現しているかもしれないが、それでも、わたしたちはその実際を、ほんとうには知ることができない。それは、現在のように記録の手段が発達した時代でも、同じことだ。
だからこそ、当事者が書いて残すことの意味は、とても大きい。
日本も同じである。戦争を知る人たちの証言を可能な限り残していかなくてはならない。
そして今、現在も、あちこちで起こっている理不尽な出来事についても、すべて記録は残されなくてはならないのだ。
公文書改竄とか日報隠蔽とか、あまりに幼稚で言語道断なのである。ああ。
恵まれていることが裏目に出ている ― 2018/05/31 23:46:49
田中慎弥著
新潮社(2007年)
田中慎弥の作品を読むのは「新潮」に掲載されていた『宰相A』以来だった。
「新潮」2014年10月号は持っている。めったにこの手の雑誌は買わないのだが、宰相Aとは時の総理大臣を暗示しているに違いないと思って興味をもったのだった。ほかにも、加藤典洋と高橋源一郎、小川洋子と山際寿一の対談も気になった。梯久美子の連載も読みたかった。
しかし『宰相A』を読み通すことはできなかった。途中から苦痛が増し、気持ちが悪くなった。冒頭から数ページは調子よく好感をもちながら読めたので、そんなふうに思わされることにいささか腹立たしい思いだった。屁理屈くさい文体は、あまり見ないタイプだし好みではないが、だからこそ母親への思慕を前面に出した冒頭にはうってつけに思えた。面白そうだと思いながら読み進んだが、背景はいろいろと現実を映し過ぎていて気分がどんよりするうえに、宰相Aの男性器の描写がちらついたところで吐き気をもよおし、このあとどう物語が展開しようと知ったことかという気になった。たぶんわたしは作家の術中にはまってしまったのだろう。真に、今この社会で起こっていること、そしてこの世界をかたちづくるに至った歴史のありさま、またわたしたちが後継に残すべき世の中の在りかたを、真に考え抜くアタマが、気構えがあるなら、このような仮定のストーリーなどすいすいと咀嚼して読み進むことができるはずなのだろう。
でも、わたしにはできなかった。
以来、世の中はヒドイ状況になるばかりなので、なおのこと、読み直す気は起きない。
ある日図書館で、日本文学の書架を眺めていて、偶然『図書準備室』という題名が目についた。
ぱらっとめくると
図書準備室
冷たい水の羊
という2篇が収録されているとわかった。
図書準備室というからには図書館とか図書室の話だろう、本の話だろう、そして冷たい水の羊とは、なんてロマンチックなタイトルなんだと、かつて『宰相A』でもよおした吐き気のことなどすっかり忘れていたこともあって、好奇心に駆られて借りてみた。
心のなかのもうひとりのわたしは、この好奇心はきっと見事に裏切られるに違いないという予想をしていて、そして見事にこっちの予想が当たったのである。
「図書準備室」は、ひきこもっていい歳になっても働かずにいる男が親戚の集まった場で語るどうでもいい思い出話である。男は非常に自虐的に、しかしいきいきと、自分の小中学生生活を描写し、ひとりの教師とのやり取りを語る。この教師が自身の過去の経験について語る、そこに至るいきさつが描かれる。ひきこもり男とその教師とのかかわりの舞台が、図書準備室である。その場所が図書準備室である、という以上の意味は「図書準備室」にはないのである。図書室でこんな本に出会ったとか教師がこの本を読めと言ったとか、蔵書にかんするほんの一文さえ出てこない。なぜ、図書準備室である必要があったのだろう。もう何度か読めばわかるのだろうか。ぜひ、わかりたいのだが。
「冷たい水の羊」は、全然ロマンチックではなかったが、面白い作品だった。やりきれなく、辛いけれど、読み応えのある一篇だった。学校関係で働く人(教師、養護教諭、用務員、教育委員会えとせとらえとせとら)と小中学生の保護者(親、祖父母、親戚)は全員これを読んだほうがいいのではないかと思われる。主人公は不憫である。そうじゃないだろと何度も声をかけたくなる。とくべつな少年ではない。むしろ恵まれていることが裏目に出ている。周囲の中学生たちも、ありがちなキャラクターである。常軌を逸しているように見える人物やシーンもあるが、現実は小説よりなんとか、ではないが現実にはいくらでも外道やろくでなしがいて、狂気に達するのはあっという間なのである。主人公は死にたいのだが、もちろん、私は生き延びてほしいと思いながら読んだ。死ねなかったという結末を期待しながら読んだ。感傷的に過ぎたのだろうか。だが主人公の胸中を思うとわたしは泣けてくるのだ。たとえば、戦争で特攻に命をとられた若者たちがいる。彼ら軍国少年たちは洗脳されていた挙句に無駄死にさせられた。これほど不幸なことはない。が、彼らを思ってもわたしは泣けない。怒りしか沸いてこない。他方「冷たい水の羊」の主人公は、自分を見つめ、親を見つめ、周囲を見つめ、自問し、答えを出し、もがきながらも行動に出て、その結果に苦悩している。彼のほうが、特攻隊員よりもずっと、悲惨である。ひとりの人間としての尊厳を踏みにじられ、生きる意味を見出せず、自分の価値をゼロとしか考えられない中学生。この現代にあってそのような存在を生み出してしまう社会の在りかたのほうが、戦時より、ある意味悲惨である。そういうふうに考えさせられたこの物語は、あまりにリアルであるのだ。が。
どちらも、さっと読んだだけでは消化不良を覚える。あと何度か読んですっきりしたいと思う。仕事で読まなくてはならない本の少ないときに、また借りよう。この本をじゅうぶんに消化したら、田中慎弥のほかの作品も読んでみたい。そうするうちに、『宰相A』を読み直す気が起こるだろうか。そのときにはAという頭文字の総理大臣が跡形もなく消え去っていてくれることを願うばかりだ。
読後感は今回もすこぶる悪かった ― 2018/05/23 01:38:52
桐野夏生 著
集英社(2004年)
「いま、何が読みたいのか」
自分でわからなくなることがある。
書店へ行っても、図書館へ行っても、どれひとつ、そそらない……ということがあるのだ(逆に、目に入る本全部ほしくなる時だってあるのだが)。
何が読みたいのかわからないのにやたらと何か読みたい時。そういうときは桐野夏生に限るのである。
とにかくどれを読んでも面白い。はずれゼロ。おおげさでなく、ほんとうにそう思う。
そんなに桐野夏生ファンなのか、といわれるとちょっと困る。自分が所有している本は文庫の『錆びる心』だけだからだ。これは短編集である。何度読んだか数しれないが、何度読んでも、初めて読むときのようにワクドキしながら読む。
そして読後感はすこぶる悪い(笑)。登場人物はみな、かなりこてんぱんにされる。たいてい、救いがたい結末が待っている。その後を想像して暗澹たる気持ちになる。
それなのに、再び読むときはまた、何事もなかったかのように初々しい気持ちで扉を開く。いや、まったくそうなんだな、面白い本って、べつに桐野夏生の小説でなくても、こういうふうに、再読だろうと五度目だろうと新鮮な気持ちでページをめくることができるものなんだ。
何か読みたいなあ、と図書館の書架の前で、あれも読んだしこれも読んだし、と思いながらふと、そうだ、桐野、読もう。と借りてきたのが本書である。
途中で止めることができなくて、一気に読み切ってしまった。
とんでもない殺人鬼の話であるが、当の殺人鬼の悲惨な生い立ちにもかかわらず、キャラクター設定が功を奏してか、このヒロインの一挙手一投足はどこかコミカルで、いちいち失笑を禁じえない。悲惨で陰惨で、救いがたい物語が、随所に撒かれた笑わせる要素のおかげで、重さが和らげられ軽く転がっていく。
笑わせる要素というのはギャグや駄洒落がちりばめてあるという意味では、もちろんない。登場人物や背景の設定が、実在する著名人、著名団体を髣髴させたり、そこに込められる皮肉を感じたりして、苦く愉快なのである。
ヒロインは人生の瑕疵の何もかもを他人のせいにして恨むだけでは気が済まず殺していく。これほどあからさまな行動をとっていてつかまらないなんてあるのかという疑問は、措く(日本の警察が優秀だなどというのは妄想)。ヒロインに殺されていく人物たちは、「顔」のない人々だ。家族はもちろん知人や友人もなく、あっても結びつきは希薄で、死亡したことが大きな出来事とはならない人々。世の中からうち捨てられたヒロインが、自分と同様に人生から足を踏み外した人、こぼれ落ちた人、行き場がない人を容易(たやす)く踏みにじっていく。
ただし、最初の殺人はヒロインの積年の恨みを晴らすかたちで実行された。この成功体験を引き金にしてヒロインは簡単に殺し続けるようになる。
アイムソーリー、ママというタイトルどおり、ヒロインは母親に謝るのである。
謝らなければならないような事態を招いてしまう。
しかし、謝る対象の「母親」を、ヒロインは認めたくない。思い描いていた「母さん」が、この女であるはずがない……。
これは母親への思慕のとあるかたちを描いた物語でもある。
対象となる母親は実体のない母親であり、慕う気持ちだけが生きる原動力となっている。
それほどに「母親」は、人にとって重要な存在なのかと自問する。わたしにも母親はいたし、わたし自身も母親だ。わたしにとってわたしの母親はもちろん愛すべき存在だったが、つねにそばにいたせいであろう、渇望したり、恋い慕い抱擁したくなったり、理想化したりするような存在ではなかった。わたしの子はわたしを母親として存分に愛してくれているであろうが、今は離れて暮らしているとはいえ長らく一緒にいたし、今でも密にやり取りしているから欠乏感はないはずだ。そしてこの世のおおかたの人々にとって母親への思慕というのはそういう穏やかで起伏に乏しく、あってあたりまえな感じの、でもたしかに温かみのあるもの、年を経ればまた感じかたの変わっていくもの、そういうものであろう。
しかし『アイムソーリー、ママ』のヒロインの母親への思慕は、あまりにもまっすぐであり過ぎたゆえに大きく屈折させられ、ある意味踏みにじられ、さらに肥大化する。
この物語に登場するほかの人物たちの、「母親」のありかた、かかわりかたもヴァリエーション豊かでめまいがする。人間はこれほどまでに多様であり、そしてその出生や生きざまがどうであれ、生き延びていく権利はあるのである。
殺人鬼は、殺した人間の人生の数だけ自身も苦労し辛酸をなめ、悩み苦しみ考えに考えて考え続けて考え抜いてもがき苦しんで一生を終えさせなければ割に合わないとわたしは思う。
物語の最後にヒロイン殺人鬼の行く末が示唆されるが、冗談じゃないよそんな簡単に片づいてもらっちゃ困る、という気分である。そう、読後感は今回もすこぶる悪かったのだった。
手を打たなければ、いつか誰もいなくなる ― 2018/05/16 22:00:28
アクセル・ハッケ 作
ミヒャエル・ソーヴァ 絵
那須田淳、木本栄 共訳
講談社(2007年)
ドイツに長く暮らす友人(日本人女性)から聞いたことがある。「私も彼女も子どもをもつなら働かない、働くなら子どもはもたないという考えかたなの」
友人が「彼女」と呼んでいるのはその近隣に住む既婚女性で、4人の子どもを育てていた人のことだ。友人自身にも一女がいた。この話をした当時のわたしがまだ20代だったか、それとも娘を産んだあとだったか、もう憶えていない。わたしはわりと頻繁にヨーロッパを旅し、この友人宅にたびたび世話になっている。友人一家が住んでいたのはけっこうな田舎で、けっして便利とはいえないのだが、この友人は、不便な道のりを経てでも会いたい人だった。相談にのってもらいたいことがあるとかいうことはなかったが、会えば必ずなにかしら「またひとつ学んだぞ」という収穫があるのだった。つまりは、彼女の人生観に、わたしは大きく影響を受けていたのだ。本人にはそんな気はなかったと思うけれども、わたしは彼女のことを水先案内人のようにとらえていた。日本で生活した年月よりも長く濃い時間をすでにドイツで生きていた彼女は、異国での立居振舞にしろ、祖国への思いの抱きかたも、わたしにとってロールモデル以上の存在であった。
だから、冒頭に掲げたセリフを聞いたときには、いささか面食らった。
いっぱんにヨーロッパでは日本に比べて段違いに男女平等が進み、労働条件にしろ、人々の意識にしろ、職種を問わず機会均等であるというふうに思いがちだが、意外とそうではない人もいるし地域もあるということを、のちのちわたしも知ることになる。だが、このセリフは、わたしにとっては「女は家で子育て」という「旧弊」を積極的に支持する宣言にも思えたのだった。もちろん、じゅうぶんに稼ぐ夫がいるなら、という注釈がつく(友人も、近隣の女性もその夫はじゅうぶんに稼ぐ人だった)。しかし、だからといって、注釈つきにしても、それが前提となってしまうと夫が子育てを「手伝う」ことそのものが賛否の対象となる。
それじゃ、ダメじゃん。
いうまでもないが、「手伝う」のではなく、父親も子どもを「育てる」行為の主体でなければならない。
『パパにつける薬』はゾーヴァの挿絵も楽しい、パパの子育てエッセイである。
パパはフルタイムで仕事をこなしながら、休日を全面的に子育てに費やしている。喜びはもちろん大きいが、なかなかへとへとになっている様子がユーモアを交えて語られる。刊行当時は世の多くの男性の同意を得たことだろうと思われる。
ただし、いま内容を読むと、やはりそれは「手伝う」というスタンスに終始している点が「古さ」を否めなく、牧歌的である。この内容に感心したり驚いたりした時代もあったのね。
しかし、それにしても、この日本語版は2007年刊行である。
原書はまず1992年に出版されていて、2006年に更新されているらしいが、いずれにしても著者のハッケは、90年初頭に3人の子育てに奮闘していたのである。
このあと、ドイツ男性の子育て観はどのように変化していったのだろうか。
わたしの友人、そしてあの田舎町の女性たちは、いまも同じ考えでいるのだろうか。
約10年前に世に出たこの本の訳者あとがきにはこうある。
《大半のパパって、たまの休みに子どもと格闘し、へとへとになりながら、来週はなんとか逃げ出してゴルフにいくぞとひそかに画策したりしているのではないだろうか。もちろんママの疲労もわかっちゃいるのだけど……。》
10年経って、このような「大半のパパ」はせめて「一部のパパ」になっているだろうか。妻とともに日常的に家事も育児も頑張るパパが目に見えて増えてきたのは認めるが、それでもまだまだ少数派だ。相変わらず、「大半のパパ」が休日のみ手伝う、という状態のままではないだろうか?
パパの意識改革の道のりがまだまだ長いとしたら、パパをアテにはできない。働く女性が圧倒的に増えてきた昨今、社会の仕組みを多方面から根底から変えていかないと、母親はみな精根尽き果て、恐れを抱いた次世代は子をもたなくなる。いや、この状況はもうとっくに始まっている。手を打たなければ、いつか誰もいなくなる。
ま、そうなればなったでそのときにはそのときなりの、危機の乗り越えかたを全員で実行していることであろう。
でも、でも、だからといって、ぎゃんぎゃん言うのを止めてはイカンと、やっぱし思うのであった。
成長する過程で忘れ去られていくに違いない ― 2018/05/13 23:51:32
ジークフリート・レンツ
松永美穂 訳
新潮社(クレスト・ブックス)2010年
レンツの作品は、ずっと前に『アルネの遺品』を図書館で借りて読んだことがあるだけだ。この『アルネの遺品』が素晴しすぎて、わたしはその後も何度か借りては読み、アルネやハンス、その親兄弟たちの心情に近づこうとした。それはなかなか容易ではないことだった。自分自身と登場人物とのあいだに生活環境やそのほかなんらかの共通項が少ないと、物語のなかの世界を生きるように読むことは難しい。とはいえ、そうして自分に引き寄せて、自分の物語として読むことが安易ではないからこそ、小説を読むことは面白いのだともいえる。『アルネの遺品』はその意味で、いくら読んでも、その悲しみをたたえた海の圧倒的な大きさに読み手は黙るばかりである。
『アルネの遺品』に比べたら、本書『黙禱の時間』は恋愛の物語でもあるので、感情移入は幾分か易しいといっていい。立場だとか身分だとか年齢だとかはまったく関係なく人は誰かに惹かれ誰かを愛してしまうものである。
『アルネの遺品』に少し似て、本作でも主人公にとって大切な存在であった人は、冒頭ですでに死んでいる。小説は、学校で行われている追悼式の模様を描写しながら始まる。誰が追悼されているのか。校長が演壇に置かれた「シュテラ」の写真に深々と頭を下げる。
《先生は、どのくらいの時間、きみの写真の前で、その姿勢のままでいただろう。シュテラ。》
「ぼく」が「きみ」「シュテラ」と呼ぶのは、校長先生が頭を下げているその写真のひとである。「ぼく」は「きみ」との思い出をたどっている。それは恋人たちの風景だ。
《ブロック先生は写真を見下ろしながら話していた。きみのことを、敬愛するシュテラ・ペーターゼン先生、と呼びながら。》
「きみ」「シュテラ」は、この学校の教師だった。「ぼく」はその「シュテラ」と恋仲だったのに、彼女は死んでしまったのだ。そして生徒のひとりとして学校で行われた追悼式に出席している。
このあと物語は「ぼく」と「きみ」との恋の始まりから不幸な事故で彼女が命を落とすまで、そしていま進行している追悼式、式のあとで「ぼく」が校長に呼び出されることなどが決まった法則もなく右へ左へと語られる。つねに「ぼく」が語り手であり、「ぼく」が初めて本気の恋を経験し大人になったことを自覚したというのにその対象は無惨に失われてしまった、その事実を受け容れられないまま、戸惑ったまま、自分はなぜ生徒のひとりとしてしか「きみ」を悼むことができないのだろうというやり場のない悲しみに、物語の最後まで「ぼく」は翻弄されている。
「ぼく」とシュテラは長い間恋愛関係にあったわけではなく、たったひと夏の恋であった。その描写からは、シュテラが「ぼく」を本気で愛していたかどうかはわからない。というか、おおいにほんの弾みでそうなっちゃった感がつよい。そのいっぽうで、「ぼく」の本気度がなかなかに高いので、「ぼく」が拙速でなくじっくりと彼女とのあいだに愛を育んでいこうとしてたなら、もしや彼女は「ぼく」を伴侶として受け容れたかもしれないとも思わせる。しかし、まあ、そればかりはわからない。わからないまま終わってしまったことが「ぼく」の未熟さを強調しているし、未熟さは純粋さでもある。高校生のそういう「青さ」を楽しむ物語でもあるが、いろいろと謎を残したまま死んでしまったシュテラは、「ぼく」の心のなかに痕跡をとどめるとしてもこの先「ぼく」が成長する過程で忘れ去られていくに違いないと思わせる点で、若さの残酷な面も言外に語っている。いまは打ち拉がれているけれど、アンタ十年後にはきっと忘れてるでしょ、と主人公に言わずにおれないのである。そして、そんなシュテラを憐れんで読んでいる自分に気づく。シュテラが「ぼく」をどう思っていようと、彼女なりの幸福を追求する時間や機会を、生きていればもっていたはずで、それをぞんぶんに駆使しないまま死んでしまうなんて。
物語はあくまでも「ぼく」の物語で、シュテラやその父親、同僚教師との関係など、その後ろ側にあるストーリーをいろいろと推測し想像をめぐらすことはできるものの、答えはまったく書かれていない。表面だけをたどったら高校生男子の、いささか辛いひと夏の恋、でしかない。だがもう少し時間をかけて読み直し、シュテラの視点で、あるいは父、あるいはほかの誰かの視点で物語全体を見つめるともっと面白いだろうと思われる。
訳者あとがきによると、レンツが82歳でこの青春物語(?)を書いたということが、ドイツでは話題になったそうだ。その頃再婚したことも。
レンツは長らくハンブルグに住んでいたそうである。
『アルネの遺品』も舞台は港町だったが、本作も同様、ヨットなど船舶の描写が多く、海や漁に知識のある人なら、事故で帆柱が折れる様子など、その臨場感は知らない者よりも真に迫って読めるのではないかと思う。海が荒れる、高波が襲う、船が岩場や港湾への入り口の壁に叩きつけられる、といった描写は、海の現実を知らない者には過去に見たことのある映画だとか、あるいは気象情報が伝える台風で荒れる海などの映像から想像するしかない。
レンツはハンブルグ住まいのあいだに、いくつものそうした海難事故を見聞したのだろう。
美しい海は、ひとつ違(たが)うとあっさりと命を奪う凶器となる。
そのことによる恐怖について、わたしはやはり知らなさすぎる。これほど水の災害の多発する列島に住んでいながら。こればかりは、なんともしようがない。
『アルネの遺品』については、ずいぶん前のことながら当ブログに書き記していたのでそのリンクを。
http://midi.asablo.jp/blog/2010/01/06/4797570
レンツは2014年に亡くなった。松永美穂さんによる翻訳にはもうひとつ『遺失物管理所』がある。それも併せてレンツをもう少し根気よく読み続けたいと思っている。
疲れた大人が読む物語である ― 2018/05/10 23:40:40
エルケ・ハイデンライヒ 作
ミヒャエル・ゾーヴァ 絵
三浦美紀子 訳
三修社(2003年)
ゾーヴァという画家をずっと前から知っていたわけではない。その名前は百貨店のホールで開催される美術展の告知で知った。その後調べてみたらすでに挿絵を担当した物語本はいくつか翻訳出版されていたし、画集も出ていた。日本では2005年と2009年に巡回展が開催されたが、わたしが娘と行った美術展は2009年のほうだったと思う。その頃から、美術展の際にショップで売られる「小物」のヴァリエーションが増え出したと記憶している(図録と絵葉書くらいしかなかったのがクリアファイルや缶ボックスやマスキングテープやマグネット等々等々)。わたしは「ちいさなちいさな王様」の缶ボックスを買いましたのよ。
そしてまたうかつなことに、映画「アメリ」で作品が使われて話題になっていたというのに、そんなこと全然知らずにいたことも、その美術展で知ったわけで、映画好きを自認しているのに時にあまりにも細部に無頓着すぎてわれながら呆れたのである。
そんなわけで、ゾーヴァの絵との出会いが出版物ではなく実物であったことは、この画家の昔からのファンの皆さんとは、多少、その作品に対する意識が異なることにつながったのではないかと思う。その絵の数々はたいへん素晴しく、迫力もあり、また物理的な「厚み」を感ずるものたちだった。そういう絵の数々にいたく感動してから既刊のゾーヴァ本を探したが、本がどれも小さくて、展覧会で観た圧倒的な迫力はどこかへもっていかれてしまっている。もちろん、挿絵にするのが前提で描かれた絵の原画は、どれもそれほど大きいものではなかっただろうと推察されるが、展覧会で大きな絵の数々を観てしまったので、本になったゾーヴァに物足りなさを感じてしまい、なかなか読む気になれなかった。
しかしながら、図書館で、目的の有る無しにかかわらず棚を眺めていると、ふとした弾みで目につき、ふとした弾みで借りてしまうことがある。このたびは、早々に目的の書籍を見つけて「ついでに何かほかに借りていこうかな」と思うやいなや目についたのであった。
ゾーヴァの挿絵が使われているが、いわゆる絵本ではなく物語の本である。物語は長くなく、クリスマスの短いお話である。しかし子どもに聴かせる話ではない。大人の読む物語である。しかも、仕事と恋と人間関係に疲れた大人が読む物語である。タイトルが示すとおりである。生きる意味を問うているならこの本を読みましょう。
物語はいきなりこう始まる。《その年はずっと、狂ったみたいに働いた。》
かつてのわたしみたいだ。《まるで生活するのを忘れてしまったかのようだった。友人にもほとんど会わず、休暇を取って旅行することもなかった。》
なかった、そんなの。仕事以外の何をしているのか毎日わたしは? ……みたいな日々だった、わたしも。《そして鉛のように重くなってべッドに倒れこんだ。》
ああ、ほんとうに、わたしのようだ。
違うのは、この主人公は「その年はずっと、」と言っているので例外的に非常識なまでに働いた年だったのだろうということだ。わたしはといえば、学校を出て働き始めてからたいていがそんな「狂ったみたいに働い」てきたような状態だ。そして主人公は離婚したシングル女性だがわたしは結婚経験のない子持ちシングルであるということ、それだけだ。それだけって、それは大きな違いではないかといわれるかもしれないが、そうでもない。主人公は疲れ果てているところにかつての夫だった男から電話を受け、クリスマスをその男の住む街で過ごさないかと誘われ、心が動く。それもいいかもしれないと、重いからだをひきずるようにして旅支度をし、彼が待つ場所まで向かおうとする。実際、もしわたしも、昔の男からひっさびさに連絡もらって会おうよなんて言われたらホイホイと、へろへろになってても、取り繕って会いにいこうとするだろう。そういう、なんつーか矜持も何もないところが主人公と自分は限りなくよく似ている。
さて主人公はクリスマス旅行の途中で買い物をし、その買い物のおかげで、道中さまざまな出来事に遭遇する。本書はその道のりにスポットを当てた物語である。若干ドタバタしていて、そんなアホな的展開といえなくもないが、しかし、いちいち奥深いのである。そして、主人公は生きることの意味を問うのである。
旅の途中、エーリカと離ればなれになった主人公は幼い頃の記憶をよみがえらせる。
《九歳だった。列車の窓のところに立って、泣いた。》
《私が泣いたのは、自分が戻ったときに果たして母親がまだうちにいるかどうかさえ、確信が持てなかったから。》
この一文に、わたしは胸の奥にすーっと刃物で細い切り傷をつけられたように気持ちになった。わたしは自分の娘にそのような思いをさせてきたに違いないと思うし、そしてまた、母の介護中には、短期宿泊施設に預ける時などに母がそのような思いをしていたかもしれないと、いまさらながら思い起こしているからだ。
上の、「私が泣いたのは」のくだりの直前には、こうある。
《泣いているのは、愛されていない子どもたちなんです。そして、子どもを四週間だけでも遠ざけることができて、母親たちがほっとしているのを感じている子どもたちだけが、泣くのです。》
こちらは愛していないはずがないじゃないかといいたいけれど、愛されたい側はそのような振る舞いでは愛していないのと同じことなのだろう。理屈ではとっくにわかっていたことだし、もち続けた「負いめ」はいつか心から相手に尽くすことでプラマイゼロにしてみせる。こちらはそう思うのだけれどマイナスが深くなるばかりで、ようし、と気合いを入れる余裕ができた頃にはとっくに手遅れなのだ。子どもは成人して独り歩きをし、老いた親は死んでしまう。Trop tard.
そして主人公は気づくのである。
《たった数時間で、エーリカは私の生活を変えてしまった。》
《人々は私をうれしそうに見つめ、私も笑い返した。》
エーリカの存在が、見えていなかったことを発見させ、忘れていたことを思い出させる。
くたびれはてて、若干自暴自棄になっていた女が、かつて愛し合った男に再会してまた心機一転生きる希望を見出して……とはならない。主人公は元夫との待ち合わせの駅までたどりつくのだが……。
「エーリカ」は、おわかりだろうが主人公の名前ではない。では誰の? うふふ。
人生に疲れていなくても、読んでください。
作品と作品が緩やかに呼応している ― 2018/05/07 23:10:49
小川洋子
角川書店(1996年)
小川洋子の小説は、読む者をすっと異界に誘(いざな)う。読者を異界へ連れていく小説などじつはそこいらじゅうにあるのだろうし、小説というものじたいを異界であるとしたら、小説を読むことはイコール異界へ連れていかれることにほかならない。それはそうなんだが、小川洋子の紡ぐ物語の場合は、わたしたちの現実と、彼女の描く異界との境界がなく、読む者はつねに異界の入り口の前に深くあるはずの淵に立たされどぎまぎしているのに、ふと気がつくととっくに淵を飛び越えて異界に身を置いている、そんな感覚にとらわれる。
本書は小川洋子の短編集である。10作品が収録されている。
表題作で最初に収録されている「刺繍する少女」の舞台はホスピス。先の永くない母親を看取るために「僕」はここに泊まり込むことになった。そのホスピスで、幼い頃、夏休みを一緒に過ごした少女に再会する。幼い頃の面影があったわけではなく、彼女の刺繍をする姿を見て、思い出がよみがえったのだった。彼女は施設にボランティアとして通っており、毎日ベッドカバーに刺繍をしていた。刺繍する彼女と話すため、あるいはただその刺繍する姿を見るために、「僕」は毎日、母が眠ったのをみはからって彼女に会いにいく。
母が亡くなり、ホスピスを引き払う段になり、彼女の姿も消えた。「僕」はもろもろの後始末や事務的な雑用を弟に任せたまま、ただ彼女を探しまわるのだが、刺繍されたベッドカバーが空いたベッドにかけられていたのを確かめただけだった。
この刺繍する「彼女」は喘息もちである。本書の最後に収録されている「第三火曜日の発作」の「わたし」も喘息だ。発作を恐れて家に引きこもっており、月に一度、第三火曜日に通院するのが唯一の外出であり、その外出でのハプニングを描いている。
この短編集の中では、作品と作品が緩やかに呼応しているように思われる。「刺繍する少女」と「第三火曜日の発作」は共通点は女性が喘息もちだということだけで、「第三火曜日の発作」の「わたし」は刺繍している様子はない。ないのだが、勝手に想像させてもらうと、刺繍していた少女は成長して「第三火曜日の発作」の「わたし」となって、苦い経験などなどを経てまた刺繍するばかりの女となって、たまたま幼い頃の記憶を共有する「僕」と再会したが、「僕」には彼女をそこに留めおく魅力はなかった……。
2番めの「森の奥で燃えるもの」は「収容所」を舞台にしている。この「収容所」ではべつに毎日過酷な重労働にさらされているとか、殺戮が行われているということはなく、全員がなにがしかの役割は与えられているが、平穏に暮らしている。その設定そのものが不気味といえば不気味である。平穏な様子でありながら、じつは、やはり、明日自分がどうなるかはわからない。
9番めの「トランジット」で、「わたし」は空港で居合わせた外国人とおしゃべりをしながら亡くなった祖父にまつわる思い出を反芻する。「わたし」の祖父は、ナチスによって収容所に送られたユダヤ人の、生還者のひとりだった。腕には、数字の焼き印がくっきり残っていた。幼い「わたし」がこの数字はなあにと尋ねた時に祖父は、ほかの誰でもない間違いなく私である印だと言い、「もしおじいちゃんが顔を大やけどしても大丈夫。ここを見てくれさえすれば、おまえはちゃんとおじいちゃんを見つけることができる」と言って孫を安心させたのだった。
小川洋子はこの短編集の刊行の前年に、「アンネ・フランクの記憶」という旅のエッセイを発表している。アウシュヴィッツを訪ねた小川は、遺構を見て「きれいだ」と感じてしまったこと、そしてそのような感想をもつことはいけないのではないかという意識に苛まれたことを書いている。
収容所は、あの時代のナチスの叡智(などという言葉を使いたくはないけれども)を結集した大きな成果物のひとつだったことは事実だ。じつに効率よく、人びとが輸送され、集められ、ある者は強制労働、ある者はガス室にと仕分けされ、じつにてきぱきと「仕事」は進められていった。大きな事業所でもあったその場所は、計算されつくした機能美を備えていたに違いないのだ。
「森の奥で燃えるもの」は、過酷な収容所の、アンチテーゼのひとつであるともいえる。あり得ない世界だが、あり得てはならなかったある実在の収容所がなかったら、生まれなかった世界である。
と、このように、どことなく作品どうしが呼び合う短編集である。そしてどの物語もやはり、え、これで終わるの、この続きを読ませてよ、という気持ちになる。異界にぽつんと取り残されるような気持ちになる。
たったひとつ、「アリア」は、自分の近い将来のことのようでもあり、あるいは娘に待っている未来のようでもあり(いやほんとに)、はたまたつい最近会った友人の人生に似ていなくもないなと思えるなど、これだけは異界ではなく、切実に現実的な物語なのだった。山間の村に引っ込んで余生を過ごすわたしのもとに、甥っ子は、毎年誕生日祝いをしに駆けつけてくれるだろうか。……やつは、しないだろうな。というのが読後感想の一部分であったのだった。
La Petite Bijou ― 2015/03/26 17:59:55

『さびしい宝石』
パトリック・モディアノ著 白井成雄訳
作品社(2004年)
20年ちょっと前のこと、雑誌をつくっているフランス人のグループに加わり、彼らの仕事を手伝うことになった。それはスタッフたちとのちょっとした関わりがきっかけだったが、はっきりいって、当時けっこう捨て鉢な気分で生きていたので、居場所があればどこでもよかった。わずかでも小遣いになるなら、どんな仕事でもよかった。覚えたてのフランス語を使えてそれなりのバイト料ももらえるのだから申し分なかった。雑誌に掲載する記事のほとんどはフランス人による寄稿で、翻訳は仏文学科の大先生たちが格安で引き受けてくれていた。私の役目は事務所の留守番や郵便物の管理だった。
まもなく、ある映画祭のため来日するフランス人ゲストを取材することになった。パトリス・ルコント。私は浮き足立った。ルコントは当時私にとって最大級の賛辞を贈っていい映画監督のひとりだった。『仕立て屋の恋』と『髪結いの亭主』の2作品によって私は完全にノックアウトされており、『タンゴ』を見逃していただけにその次の新作を映画祭でいち早く観られるだけでもめっけもんどころではなかった。監督その人に会えるなんて。
「ルコントに何を訊きたい?」
「まなざし、の意味かな……」
「まなざし?」
「ルコントの映画の人物って、やたら人を見つめるんだよね、じーっとね。じーっと視線を送るの、日本人はあまりしないし」
「ふむ、なるほど。いいところに目をつけたな。それ、ちゃんと質問しろよ」
「え? あたし、ついていくだけでいいんでしょ」
「いちおうさ、ウチの雑誌、日仏の文化的架け橋になるとかなんとかお題目つけてんだよ。そこで仕事してるんだしさ、もうちょっとコミットしろよ」
「ぐ」
「せっかくしゃべれんのに、フランス語」
「がが……」
というような会話を会場へ行く電車の中でするもんだから、編集長、そんなの言うの遅いよと抵抗してみたがダメだった。取材を全部やれとは言ってない、でもその「まなざし」の話はお前が口火を切れといわれ、ポケット仏和−和仏辞書を繰って頭の中で質問文をつくった。
懐かしい思い出だ。
私たちはほんの数分しか時間をもらえなかったが、インタビューはすこぶるスムーズに進み、有意義な時間を得た。売れっ子監督でもあったルコントは、どのような問いにもあらかじめすべて用意してあったようにするすると答えた。とても論理的で(フランス人はたいていそうなんだけど)、口を開くたび、起承転結の完全な小話を聞くようでもあった。
私たちは彼の新作を映画祭の会場で観賞した。映画を観たのが取材より先だったか後だったかを思い出せない。たぶん、取材の後だっただろうと思う。ルコント本人に会う前に観ていたら、ずいぶんと気の持ちかたが違っていたはずだからだ。
新作は、『イヴォンヌの香り』だった。
私はこの作品にとてもがっかりしたのだった。
男ふたりに女ひとりの三角関係なので、そこは女に魅力がないと成立しない話のはずなのに、この女優が全然ダメだった。フランス人好み(たぶん)の整った小づくりな顔立ちで、美人なんだろうけど、なんといえばいいのだろう、しっかり肌を露出しているのに色気がない、ベッドシーンもあるのに色気がない。全然色気がない。艶(つや)とか、艶(なまめ)かしさとか、じわっとにじみ出るような潤いがなくて、かすかすな感じ。言葉がきたなくて申し訳ないが「しょんべんくさい」のだ。しょんべんくさいが悪ければ「ちちくさい」といおうか。「未熟」とか「稚拙」とかはあたらない。まだ若いから、芸歴がないから、といった素人くささやキャリア不足ではない。この女優はたぶん10年経ってもこんな感じのままに違いない、と思わせるほど、どうしようもないほどの「およびでない」度満開の、魅力のなさ。
なぜこの女に老いも若きも振り回されねばならないのか。……この問いは物語に感情移入して発するのではない。この女優の存在のつまらなさのせいで、映画全体が退屈なものになってしまっている。戦争が背景にあり、かつてのフランス社会に厳然とあった階級制度の名残りがちらつく。よく準備された申し分ない設定のはずの映画で、つまらぬ自問を発するしか感想のもちようがないなんて。
時代や身分がどうであろうと所詮男と女がからみ合うのよ、といったふうのいかにもなフランス映画といってしまえばそれまでで、ルコントの映画はつまりそんなのばっかりなんだけど、でも彼は俳優にその力を最大限に発揮させて従来の何倍も魅力あふれる人物に仕立て、台詞と、構成と、カメラワークと、編集の才で、ありふれたメロドラマを極上の映画に仕上げるシネアストなのだ。
なのに、これ。『イヴォンヌの香り』。
『イヴォンヌの香り』の原作はパトリック・モディアノの『Villa triste』である。パトリス・ルコントは作家モディアノを非常に敬愛し、愛読していると取材時にも話していた。もちろん私は、モディアノの名前を聞いても「誰それ、何それ?」状態であったが、のちに映画のクレジットをチラシで見て、その名前を確認はした。パトリック・モディアノ。ところが不幸なことに、『イヴォンヌの香り』に幻滅するあまり、その幻滅に原作者の名前も巻き込んでしまった。1994年。せっかくパトリック・モディアノと出会いかけたのに、顔も見ないで私は席を立ってしまったのだった。
ずっと後になって、図書館のフランス文学の書架にモディアノの名前を見つけたとき、どうしても読む気が起こらなかったのだが、そのときなぜ読む気になれないのかがわからなかった。『イヴォンヌの香り』の原作者であることなど、とうに忘却の彼方なのだった。なんだかわからないけど「お前なんかに読んでもらわんでええ」と本の背に言われているような気がして、私はモディアノを手に取らずにいた。
ところがある日、モディアノとの再会は強引に訪れた。『さびしい宝石』と書かれた本の背に、原題とおぼしき「La Petite Bijou」という文字もデザインされていた。おおお、ぷちっとびじゅー、と私は思わず口走っていた。というのも、私は娘が生まれてから3年ほどのあいだ、ハードカバーのノートに子育て日記をつけていたが、そのタイトルを「Ma petite bijou」にしていたのだ。私の可愛い宝石ちゃん、くらいの意味だが、「ビジュ」の語感がいかにもベビーにぴったりで、我ながら気に入っていたのだった。これを読まないでどうする。私は小説家の名前も見ないでこの本を借りて読んだ。
19歳のテレーズは幼い頃母親と生き別れ、母親の女友達の家に預けられて育つ。母親は彼女を「La petite bijou(可愛い宝石)」と呼んでいた。いまテレーズはパリでなんとかひとり暮らしを始めようとしている。ある日混み合う地下鉄の駅で母親に似た人を見かけ、その後をつけていくが……。
パリの雑踏、夜の舗道の暗さ、親切な人、得体の知れない人、自分の中で交錯するいくつもの記憶、自分でもとらえきれない、母親にもつ感情。
当時娘は小学生で、私は仕事も忙しく、娘の学校行事やお稽古ごとなど校外活動など、かかわることも増えてきりきり舞いしていた。そんなときに、親にも社会にも見捨てられてその日を生きるのが精一杯の少女の、非行に走るでもなく男を手玉に取るでもなく人を殺すでもない、誰も知らないところでただもがくだけの毎日を描写するこの小説を、ぞんぶんに味わって読めるはずもなかった。親に捨てられ、ろくに学校にも行けず、都会に放り出された19歳。足許のおぼつかない、いつ道を踏み外してもおかしくないような状況で、それでも善悪は心得ていて、妙にお行儀がいい。もって生まれた性格なのか、それが幸いして少女は人の親切を得てかろうじて立っている。その、紙一重の危うさを生きる心象風景を描いた小説の世界に入っていけるわけもなかった。私には、この本の中の「ビジュ」のような19歳に我が娘がならないようにせんといかん、という程度の読後感しかなかった。というより、19歳なんて、想像の域を超えていた。それに、テレーズは、私の19歳の頃とはまるで似つかぬ生活をしていた。そして娘もいつか19歳になるのだけれども、想像するその姿とテレーズとは、まるで重なるところがなかった。
私はモディアノを、その素性も知らず強引に自分に引き寄せてみたけれども、何の手応えをも感じないですっと手を離してしまった。このときも、『イヴォンヌの香り』の原作者だとは気づいていないのである。
先月、娘が19歳になった。
だからといって、テレーズを思い出したわけではない。
遡って、昨年のノーベル文学賞に、パトリック・モディアノが選ばれた。村上春樹が有力視されていたらしいので、「期待に反し受賞は仏作家モディアノ」という見出しが新聞を飾った。
聞いたことのある作家だなあ。
それ以上の感想はもたなかった。
しかし、ふだんあまり小説を読まないので、ノーベル賞受賞作家は、短いものでもいいからひとつくらいは読むようにしている。で、例外なくノーベル賞受賞作家の作品は、なかなかに奥が深くて面白いのである。さすがなのである。
資料を借りにいった図書館で、ついでに何か読もうかなと仏文学の書架を眺めていると、「パトリック・モディアノ」の名前が目に入り、そしてすぐに『さびしい宝石』が目に入った。
おおおおお、Ma petite bijou!!!
モディアノだったのか!
その並びに、『イヴォンヌの香り』も収まっているのに気づいた。
うわああああ、イヴォンヌ!
そうだ、モディアノだ、モディアノだったぞ原作者!
と、バラバラだった記憶がひとつにつながったのだった。
私は見覚えのある『さびしい宝石』の表紙をめくり、カバー見返しに「なにがほしいのか、わからない。なぜ生きるのか、わからない。孤独でこわがりの、19才のテレーズ——」というキャッチコピーを見つけ、迷わず再読を決め、借りたのだった。
10年ほど前におおざっぱな読みかたしかしなかった作品は、いまははっきりとリアルにメッセージを投げているように感じる。それは、いまのこの私に対して、という意味だ。19歳の娘がいま異国で、わくわくしながら暮らすいっぽうで不安におののき、愉快な友達に囲まれながらもホームシックに苛まれ、自分がとる進路はこれでいいのか、自分も含め誰も明快な答えを出せない中でそれでも歩かなくてはならない得体の知れない圧迫感に息が詰まりそうになっている。テレーズと何も変わらないじゃないか。そうだ、同じことだ、私にしても。19歳の頃、何かに追い立てられるようにして、誰もが向かっている方向へ一緒になって歩きながら、心の奥のほうで、違うこっちじゃないと、気持ちだけが引き返していた。引き返したけれどそっちに目的地があるわけでもなかった。道しるべはない。道しるべは自分で立てていくものなのだ。でもそんなこと、わかるはずもなかった。だからもがいていた。なぜここでこうして生きているのか、なぜ生まれてきたのかわからないまま。テレーズと、そっくりだ。
テレーズのもつ、生き別れた母に対する複雑な思いは重層的で解き明かし難い。母の存在はとっくにない。実体として掴もうと欲しても叶わない。だが母は弱々しい糸のような頼りない記憶の連鎖としてテレーズの脳裏に在って、テレーズをしばっていた。自分の中で記憶を断ち切るしか、解放はされない。解放されなければ、テレーズが自分の生を取り戻すことはできない。
といって、テレーズがはっきりそんな目的意識をもって邁進しているわけではない。どうすればいいのか。どうもしなくていいのか。そもそもなにをしたかったのだろう?
《もう何年も前から、わたしは誰にも何ひとつ打ち明けたことがなかった。すべてを自分ひとりで背負い込んできたのだ。
「お話しするには、複雑すぎて」と、わたしは答えた。
「どうして? 複雑なことなんて、なにもないわ……」。
わたしは泣きくずれた。涙を流すなんてことは、あの犬が死んでからはじめてだった。もう十二年くらい前のことだけれど。》(『さびしい宝石』80ページ)
読み終えて、というよりページをめくるたびに、私は娘を抱きしめたくなった。1行ごとに、娘の顔を見たくなった。テレーズが息をつき、言葉を口にするたびに、娘の住む町へ飛んでいきたくなった。
Quel début d'année atroce... ― 2015/02/28 16:17:34

谷川俊太郎 著 柳生弦一郎 絵・装本
福音館書店(2007年33刷/初版1982年)
今日で2月も終わりである。雪の多い正月を過ごし、雪の話ばかりしていたのに、めまぐるしく日々が過ぎていき、明日から3月。
ほんとうに、なんということだろうと思う。何が何でも、12月の選挙でひっくり返さなければならなかった。幼稚で狡猾な独裁志向のただのわがまま坊主には退場してもらわねばならなかった。ほんとうに、この国の大人たちの危機感のなさ、視野の狭さ、その「自分のことで精一杯」ぶり、もとよりこれは自戒を込めて言うんだけど、あまりのことに呆れ果てただ悲しい。
悲しいときに、よく私はこの本を開く。この本にはただひらがなの言葉がつらつらと並び、ときおり、子どものいたずら描きのような、それでいて味のある、人物の肖像が挟まれる。そうしたひらがなの文字を目で追い、目で追うほどに言葉になるのを追い、言葉が連なるままに詩篇となるのをただ吸収する。息を吸うように読み、息を吐くようにページをめくる。
そうするだけで、いつのまにか心が落ち着きを取り戻すのを感じる。こんなに毎日惨いことが起こる世の現実に私の精神はひどく安定を欠いているのだが、一時的にせよ、いやまったく一時的に、なのだが、穏やかになれる、心底。安定を欠いていると言ったが、なにも朝から晩まで不安に苛まれ泣いているわけでも、ホゲーとしているわけでも、どうすればわからなくなってうろうろしているのでも、ラリっているわけでもない。平静を装い、毎朝同じ時間に起き、いつもと同じ一日が始まると自分にも娘にも母にも猫にもいい、三度の食事を支度し食べ、洗濯や掃除などハウスキーピングにいそしみ、商店街で野菜の値段を見比べ、大人用紙パンツのセールに目を光らせる。そんな合間に、依頼された原稿を整理したり、自分の書いたものの焼き直しをしたり、面白そうな仏語本を渉猟する。娘のメールを読み、返信をする。優先順位の高いことというのは、たしかに、何よりもこうした自分と自分の身近な者たちのことばかりであって、そしてほんらいそれでよいのである。家のそと、町のそと、地域のそとは、私なんかが心を砕かなくても万事順風満帆に事は運び憂いは流れ、いいとこ取りをされて均されて、治まるというふうに、かつては決まっていたのであった。いや、かつてもこの世には恐ろしいことや許されないことや悲しいことがたしかに次々起こっていたのだけれども、そのたび、そのときも私の心はおろおろしていたのだけれども、世の中には必ず賢明な知見が在るべきところに在り、どこかで防波堤となっていたのであった。
いまはその防波堤が見当たらない。どこにも。あかんわ、もう。あかん。
『みみをすます』を開く。ひらがな長詩が六編収められている。ひらがなだけど、これらの詩は子ども向けではない。この本を買ったのは、自分のためだった。谷川俊太郎の「生きる」が小学校の教科書に掲載されてたか授業で取り上げられたかなにかで、娘が暗誦していたときに、その「生きる」よりもいい詩が俊太郎にはあるんだよ、と「みみをすます」のことを言いたかったんだけど、詩篇は手もとになく、ネット検索で見つけた詩篇のすべてをダウンロードしたかコピペしたかの手段でテキストとしていただき、ワープロソフトに貼って、きれいなフォントで組んで、A3用紙にプリントして、壁に貼った。とっくに貼ってあった「生きる」の横に、「生きる」よりはるかに長い「みみをすます」はとても暗誦できるものではなかったが、断片的に拾うだけでも意味があると思って、「みみをすます」を貼った。娘は「みみをすます」も声を出して読んでいたが、語られていることはまだまだ幼かった彼女の想像を超える深淵さで、圧倒されてつまらなかったに違いない、そのうち熱心には読まなくなった。
「みみをすます」は次の4行で始まる。
みみをすます
きのうの
あまだれに
みみをすます
生活音を想像できるのは以上の4行のみで、次のパラグラフからは壮大な人類の歴史に思いを馳せていくことになる。《いつから/つづいてきたともしれぬ/ひとびとの/あしおとに/みみをすます》。
ハイヒールのこつこつ
ながぐつのどたどた
これくらいはわかりやすいけど、《ほうばのからんころん/あみあげのざっくざっく》や《モカシンのすたすた》など、現代小学生に自明ではない言葉が出てくる。すると、現代っ子の悪い癖で思考を停止させ、調べもせず、考えるのは停止して語の上っ面だけを撫でていく。長じて、知らない言葉をすっ飛ばしてテキストを読む癖がつき、小説だろうと論評だろうと漫画だろうと、そうした読みかたでイケイケどんどんと読み進み、読めていないのに読んだ気になる。
ま、いまさら仕方ない。
はだしのひたひた……
にまじる
へびのするする
このはのかさこそ
きえかかる
ひのくすぶり
くらやみのおくの
みみなり
ここから詩は古代史をたどる。恐竜や樹木や海流やプランクトンが幾重にも生まれ滅んで、そして一気に自分の誕生の瞬間を迎える。《じぶんの/うぶごえに/みみをすます》《みみをすます/こだまする/おかあさんの/こもりうたに》
谷川俊太郎は、私の亡くなった父と同じ生まれ年である。昭和20年は13、4歳だった。敗戦時に何歳でどういう社会に身を置いていたかでその後のメンタリティは大きく変わるので、父と同じように少年時代の俊太郎を見るのは失礼きわまりないのだけれど、戦争はそれなりに当時の少年の心を大きく占める関心事であったに違いなく、そしてそれが無惨な終わりかたをしたこと、そして周囲の大人たちが思想的に豹変を見せたりしたことはショッキングな事態だったと思われる。父は、玉音放送に涙を抑えきれず、でも泣いているのを母親や兄弟に見られたくなくて部屋の隅っこで壁に向かって、声を立てないように気をつけて泣いたと言っていた。しかし、俊太郎の両親や親戚はいわゆる賢明で動じない人びとだったのであろうか、戦時は時勢にしたがい行動し、やがて粛々と敗戦を受け容れ時代の変化になじんでいったようである。母親に溺愛され、自らも母に深い思慕を抱いていた俊太郎は、一体になりたいとまで欲した母に代わる存在がやがて現れることを恋と呼ぶというようなことを、エッセイを集めた『ひとり暮らし』(新潮文庫)の中で述べている。家族愛に守られ成長した俊太郎は、戦前、戦中、戦後を、あからさまではなく静かに、詩の中に書き記していくのだ。
うったえるこえ
おしえるこえ
めいれいするこえ
こばむこえ
あざけるこえ
ねこなでごえ
ときのこえ
そして
おし
……
みみをすます
うまのいななきと
ゆみのつるおと
やりがよろいを
つらぬくおと
みみもとにうなる
たまおと
ひきずられるくさり
ふりおろされるむち
ののしりと
のろい
くびつりだい
きのこぐも
つきることのない
あらそいの
かんだかい
ものおとにまじる
たかいいびきと
やがて
すずめのさえずり
かわらぬあさの
しずけさに
みみをすます
(ひとつのおとに
ひとつのこえに
みみをすますことが
もうひとつのおとに
もうひとつのこえに
みみをふさぐことに
ならないように)
いま引用したくだりは、「みみをすます」のなかでも最も好んで反芻する箇所である。ヒトは自分の耳に心地いいものしか聴こうとしない生物である。でも人であるからこそ、聴きにくい音や聴きづらい声も傾聴できるのだ。
このあと「みみをすます」は十年前のすすり泣きや、百年前のしゃっくりや、百万年前のシダのそよぎや一億年前の星のささやきにも「みみをすます」。
でも、そんなふうに壮大な物語に思いを馳せつつも、《かすかにうなる/コンピューターに》《くちごもる/となりのひとに》「みみをすます」。
最後の一行まで読めば、気持ちが未来へ向くように、とてもよくできている。それでも時は流れ、風は吹き、水も流れ、命が生まれるのだと、そこには少し諦念を含みつつ、安寧に満ちた気持ちになる。
つづく「えをかく」という詩も、「みみをすます」に似ている。耳を澄まして聴く行為が絵に描くという行為に交替していると言ってもいい。自分を描いたり、草木を描いたり、家族を描いたり、自動車を描いたりしていきながら、《しにかけた/おとこ/もぎとられた/うで》を描く。《あれはてた/たんぼをかく/しわくちゃの/おばあさんをかく》。
「ぼく」という詩がつづき、「あなた」という詩があり、「そのおとこ」「じゅうにつき」とつづく。
いま、いちばん人の心を裂くように食い入って響くのは、「そのおとこ」かもしれない。男でも女でも、「そのおとこ」でありうる。私たちはそれぞれが奇跡の巡り合わせで生きている。今月19歳になった私の娘が、過激派組織に参加するために家出したロンドンの17歳の少女であるわけがないと、どうして言えるだろう。たったひとつのボタンの掛け違いが、人の歩くみちを簡単に遠ざける。いつもビデオカメラを抱えて旅をしていた私の友人が、あの殺されたジャーナリストにはなり得なかったとは言えないのだ。利発でやんちゃな隣の男の子が、河川敷で血まみれになっていた少年であるはずないなどとは、とうてい言えやしないのだ。彼我を分けるのは紙一重のいたずらに過ぎない。
うまれたときは
そのおとこも
あかんぼだった
こんな当たり前のことを、誰もが忘れている。
もしじぶんに
なまえがあるなら
おとこにも
なまえがある
こんな当たり前のことを、みんな忘れようとしている。
だから、『みみをすます』を開いても、心穏やかにはなれない自分に、やり場のない憤りを感じ、悲しみがこみ上げる。どうすればいいのだろう、こんなに惨い始まりかたをしたこの年を、どんな顔をして、どんなふうにふるまいながら、近しい人びとを励まし元気づけ食べさせながら、自分も凛として生きていくために、どうすれば、ほんの少しだけ転がる石ころやゴミに気をつけるだけでとりあえず歩くに支障のない道を歩くように、暮らしていくことができるのだろう。幾度も幾度も開いては、心を潤してくれていたこの本が、いまは傷口に塩を塗るように、心の壁を逆撫でする。
On a toujours une conscience tourmentée, cela ne dépends pas du tout de l'âge. ― 2014/04/25 00:16:56
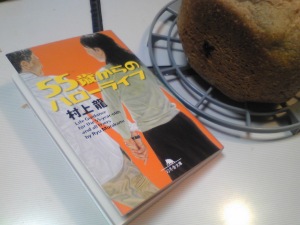
村上龍著
幻冬舎文庫(2014年4月)
行きつけの書店(けっしていちばん好きな書店ではないが)で前にもらった金券100円分があったので、文庫本でも買おうと立ち寄った。その書店のレイアウトは、会社勤めの若い男女を意識しているということのよく伝わる、わかりやすい配架になっている。こっち向いたら政治経済社会、そっち向いたら京都本著名人本スピリチュアル系心に残る言葉系。私はいつも、出入り口付近のその「参道」はすっと抜けて、実用書(旅行、料理、手芸)の壁または思想・哲学・文学系書架を眺める。買うことはほとんどない。誰が、どんなことを、どんな装幀の本の中で述べているのか、その概略をつまめたらそれでいい。いや、ほんとうは買いたいのだ、目についた本を全部。でも、我が家は私の蔵書のせいで敷居も鴨居もしなって傾き建具を引くことができないありさまゆえ、これ以上本を増やすわけにはいかない。と、けなげにもいつも諦めているのである。涙をのんでいるのである。……というのは、ほとんど嘘である。たしかに欲しい本全部は買っていない。全部は買っていないが、さんざん吟味した挙句、これだけ買うわごめんね我が家、とつぶやきながら究極の一冊を手に、それでも書架の前にしばし立ちすくみさんざん逡巡する。いったいどのくらい時間を費やすつもりなんだ早く決心してレジへ行け、と己に言い聞かせてやっとキャッシャーに足が向く。……というのはごく稀なケースである。私はたいてい時間に追われているので、そんなに贅沢に時間を費やして本を買うかどうかを迷い悩み続ける余裕はないのだ。したがって、どうしよっかなエエイ買うてまえ〜と2、3冊つかんでちゃっちゃとレジに並んでいる、というのがほとんどのケースなのである。これ以上本を増やすわけにいかないと自分に言い聞かせるようになってからもう幾年も経っている。その間、言い聞かせているのはいったい誰なのよと自問するのも時間の無駄とばかりにおおおっこれはっよし買うでえっと衝動買いに近いというか衝動買いばかりで本を買うので、本は増える。衝動買いするのは装幀の美しい本が多い。そして中身はチョー軽薄orチョー冗長orチョー説教臭いというわけで結論チョー期待外れ、だったりするので、男とおんなじだ、なんてあたしは本を見る目がないのだろう、と打ちひしがれたりする間もなく増えた本に唖然として溜め息をついている。ここ何年もの間にたしかに少なくない本を古本屋に売ったけれども、やっぱ本は増えている。私はけっして蔵書家などではない。でも我が家のキャパは超えている。しかしそうした厳しい現実から逃避するのは大得意である。で、今回のように、よく空が晴れて陽光麗しく、財布の中には金券、なんて日は、我が家の実情を忘れてルンルンと本屋へ向かうのだ。
最近の文庫は漫画単行本(コミックス)みたいな表紙が増えて、子ども向けアニメのノベライズなのかライトノベルなのかエロ漫画なのか、いや文学賞受賞作家のシリアスな小説だった、みたいなケースが多々ある。紛らわしい……。いくら文庫でももうちょっと装幀、真面目に考えようよ。そんなわけで、私は文庫に限っていえば衝動買いはしない。美しい装幀なんかないからだ。文庫の場合は、図書館で読んだ単行本にいたく感動して忘れられず、どうしても欲しいけどあの分厚い単行本は高いよな……と思っていたら文庫になっていた!よしゴーバイ!!みたいな時に限るのである。……というのは今回の場合まったく当てはまらなかった。文庫の書架の前へ来て、ケバい表紙たちに辟易しながら、なんやこれ、なんやこれ、もうちょっとさ、しゅっとして気の利いた表紙はないのんかい、持ち歩けへんやんこんなん、と心の中で悪態をつきながら、やっぱやめとこと通過しかけて、ある本に目が釘付けになった。それが本書だ。
55歳のハローワークやて、ぷぷぷっ、今のあたしにぴったりやん(私は目下プー子〈失業女〉であるから)、さすがはリュウね♪、あら、これ小林薫ちゃう? そうちゃう? そうやん、小林薫でドラマ化って帯ついてるやん、そうなんふーんテレビは見いひんけど小林薫やて、ええわあ、と、私はそのまま考えを反芻することなく、平積みになっていた本書をガッとつかんで、文庫を生まれて初めてと言っていいだろう、衝動買いした。
表紙はイラストで、熟年男女が手をつないでいる後ろ姿だが、斜め後ろから見える男の目元が小林薫だった。私は小林薫を激しく好きである。状況劇場に所属していた頃からのファンである。おっさんになってもほんまにええ男である。
平日の昼間のせいかレジカウンターにはキャッシャーがあまりいなくて、しばし列の後ろで待った。そのあいだに、表紙、そして帯をよく眺めると、55歳のハローワークじゃなくて『55歳からのハローライフ』なのだった。ワークじゃなくてライフ(笑)。ワイフでもなくてライフ。なんやねん、それ。あ、そうか。再就職の話ではなくて、人生の再出発の話なのだ。
子どもが成人して一段落した時にふと配偶者を眺め、「嫌」だという思いが募って離婚に踏み切る。定年前に会社をリストラされるが再就職の望みは薄い。早期退職して夫婦で旅行したかったのに妻は乗り気でなく。ある日ふと出会った女、熟年を迎えて生まれて初めて女にときめいたのに。とか、どれもこれも、身につまされる(笑)。
中編小説が5編収録されていて、どれも、読ませる。さすがはリュウね。本書には、いつもうじゃうじゃ出てくる変態オヤジは出てこないが(ひとりだけ出てくるが主要人物でない)、そのぶん、まともでまっとうな一小市民の人生にこれほどまでに苦悩と困難があるのか、でも、そうだよな、みんなそうだよなと、うんうんわかるわかると読み進むのである。読み進むが、結末まで来て、なんだか説教臭い終わりかたに、釈然としない。村上龍は述べている。この小説の主題は、中高年にエールを送ることだ。しょぼくれてないで、顔をあげて前を向いて、まだまだ続く未来への道を歩こう。そう元気づけるために書いたという。主人公たちはみな作家と同世代で、作家は非常なシンパシイを感じつつ書き進み、読者がよしオレもアタシも頑張ろっと前向きになってくれたらいいと願った、みたいなことを述べている。
ま、それはいいけど。
最後の5行くらいで、妙に主人公が希望に満ちたり、再出発を誓ったり。つまりは、いい方向へ向かって終わるのだが、中編小説集でどれもそういうふうに終わられると、ちょっとつまらない。この中編小説集の趣旨が最初から55歳へのエールだからしょうがないと言えばしょうがないのだけど、救いようのない話がひとつぐらいあってもいいのに(笑)と思うのは私だけだろうか。
思えば村上龍の作品は、変態オヤジがよく出てくるとはいえ、どちらかというと未来に希望のもてる終わりかたをするものが、もともと多いかもしれない。ここで引き合いに出すのはあまりに唐突だが、村上春樹はラストで読者を突き放して置いてきぼりにするのが常套手段だ。けったいな話が、それで妙にリアリティに満ちる。
本書の物語はいずれもたいへんよくある話で、自分の身に起こってもおかしくはなく、だからそれだけに、さまざまなエピソードののちに、主人公がわかったふうなことをつぶやいて終わるかたちをとっていることで、リアリティが減じている。残念。物語の起伏や挿話の運ばれかたも隙がなく、とても面白い。小説ってこう書くのね、の見本みたいである。でも、ひとつぐらいは主人公とその相方が奈落の底に落ちる話でもよかったのに(しつこい?)。
《うんと遠くにいる相手のところまで行って大切な何かを伝えるって、それだけですごい価値がある気がする。》(63ページ「結婚相談所」)

