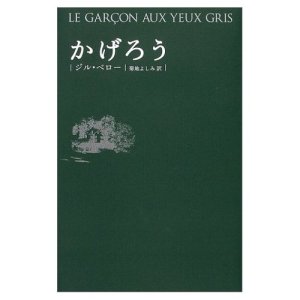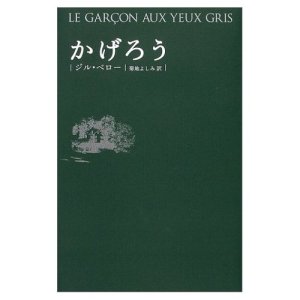『かげろう』
ジル・ペロー著 菊地よしみ訳
早川書房(2003年)
久しぶりにフランス小説らしい小説を読んだ気がする。これはいつか書いた
『優雅なハリネズミ』と一緒に借りたんだが、『優雅なハリネズミ』を読むのに思いのほか時間がかかったのに比べてこちらはあっという間に一気読み。そもそも短編(中編? ここらへんの定義はとんとわからん)をむりやりその一編だけで単行本にしたような装幀ではある。
なぜ読む気になったかというと、原題が『灰色の目の少年(Le garçon aux yeux gris)』なのになんで邦題が『かげろう』なんだろうと思ったのと、第二次大戦下の物語であることがカバー見返しを読んでわかったからである。ちょうど無料映像配信で『戦場のピアニスト』を観たのが記憶に新しく、気が滅入るとわかっていても、戦時ものを観たり読んだりしたくなるアブナイ枯渇期というものが定期的に訪れる私である。
私はジル・ペローという作家について何も知らなかったが、たいへんな大著作家であるようだ。解説によると、フランスでは「あの」ジル・ペローがこんな小説を書くのかという好意的な驚きで迎えられたらしい。そういう先入観を少しももたないで読むと、なかなかええとこ突くやんかジル君、ぽんぽん、と肩を叩きたくなるほど、小粋な逸品ぶりに嘆息である。
淡々とした文体だが、いたずらにアップテンポであるとかスピード感があるとかでなく、しっとりとした仏文学らしい湿気を帯びているのが、訳文にもにじみでていて秀逸である。湿り気を帯びながら、それでいて心理的な乾きを感じさせる描写は作家の力量によるところ大であろうが、それを日本語で再現している訳者の力量も相当である。原文と訳文の力関係がバランスを保っているとき、和文を読んでいても仏文が透けて見えるような感じを覚えることがある。今回は、どの箇所かは忘れたが、語り手でもあるヒロイン(若く美しいと思われる人妻)のモノローグに、仏語が透けて見えてなおかつ違和感を覚えた表現が数箇所あった。なんといえばよいのか、全体にフランス小説らしさに満ちながら、細部にフランスらしさを突き放したような表現が織り込んであり、それは原作云々ではなく訳者のスタイルなのであろう。
かげろうは「陽炎」? それとも「蜉蝣」? はたまた「蜻蛉」?
「蜻蛉」といえば優柔不断な薫君が浮舟をうじうじ思う一帖のタイトルである。
いうまでもないだろうがもちろん、本書『かげろう』は宇治十帖とは似ても似つかない。
しかし、とらえどころのない愛する対象のことを、日本語版編集チームがかげろうと表現したとしたら、この「かげろう」は「灰色の目をした少年」のことであるにちがいなく、それなら、束の間の情事の代名詞のような浮舟と灰色の目の少年には通ずるものがあると思えるのである。まさかジル・ペローも源氏物語と比べられるとは思っていなかったに違いないけど。
でも、残念ながら、小説からは「かげろう」という単語を想起し難かった。
もしかして原書をきちんと読めば、訳者や編集者がこの小説にかげろうという邦題をつけたくなった理由がわかるかもと思い、また、久しぶりにじっくりと文学作品を読みたくなったこともあり、渡仏の際にはこの原書を買ってこようと思った私であったが、さらには書店フェチを自認する私のはずだったが、パリでとある大型書店に入ったとたん目眩を覚えたのであった。フランス語のタイトルがぎっしりと並び積み上がり、ふと、それが、自分に向かって崩れ落ちてきそうな幻想に苛まれ、そう思うと書物を手に取るどころか、表紙の仏語を見ただけで過剰な満腹感に襲われて、うううもう二度とフランス語なんか見たくねえ、みたいな気になり、実際に一度も書店らしい書店に入らずパリ滞在を終えてしまった。もったいないことをした。でも、それどころじゃなかったんだもん、しょうがねえよな。
ツーリストにあふれ返る街を眺めながら、ここもナチスの爆撃に遭い、ズタズタにされた無辜の民らの死骸が散らばっていたなんて想像できないなあと漠然と思った。私のまちは戦火に遭わずに済み、おそらくそれゆえに、まちの活力といった類いのエネルギーを再構築するチャンスを逸したために、なし崩しに伝統だの歴史だの景観だのが失われていくのを、もはや誰も止めることができないのだ。
えーと、そんなことはともかく。
とあるエリート軍人の妻はその留守宅を預かっていたが、いよいよナチスの爆撃が居住地にも迫ってきて、幼い二人の子どもを抱えて戦火を逃れるためパリ市街地を他の市民とともに逃げ惑う。目と鼻の先で人々が体を撃ち飛ばされて倒れていく。体を伏せては走り、を繰り返しながら力尽きる寸前、敏捷な動きをする灰色の目をした少年が彼女ら三人をみちびき、母子は九死に一生を得る。足の感覚がなくなるほど歩いたのち、4人は空き家を見つけて隠れ住む……。
得体の知れない不思議な少年はときどき外出してはどこからか衣服や食糧を調達してくる。母子三人はいつの間にか少年に頼り切っている。突然フランス兵の訪問に遭い、無防備に対応した主人公を危機一髪で助けたのも、少年である。主人公は無性に彼がいとおしくなるのである。
というのがだいたいのあらすじ。このあとの展開は想像いただけるであろう。ね、とってもフランスチックでしょ。しかしなかなか重層的で奥が深いのだよ。本書は映画化されているが、映画の情報を見る限り、本書を原作としていながらかなりの変更が加えられており、今言った「重層的」な部分なんぞはきれいに省略されているようなので、まったくべつもんと思ってよさそうである。
べつもんだが、それはそれで映画としても結構秀作らしい。『かげろう』というタイトルでDVDになってます。