Poisson d'avril ― 2014/04/01 22:23:05
けさ、友達に会いに行くために阪急電車に乗ったんだよ。そんなに混んでなくて、座席はぽつ、ぽつ、と空いていて、どっちに座ろうかなとほんの百分の一秒迷ったね。私の前にいた若い女の子がためらわずすたすたすたと進んで車両の真ん中あたり、同じような若い女性とおぼしき茶髪の頭部が見える座席の隣にすっと座った。それにつられて私も前に進みそうになり、茶髪ガールのすぐ斜め後ろに空席を見つけたのだけれど、ふとその空席の隣にはすでに背広の男性が座っていた。う、と思って自分のすぐ脇を見下ろすとそこにも空席があり、その隣を占めていたのも背広の男性だった。私はそれ以上前に進むのをやめて即座にすぐ脇の座席に身を沈めた。茶髪ガールの斜め後ろの背広と、今や私の隣にいる背広との違いは、前者はオヤジで後者は若者であるという違いに他ならない。前者がオヤジであるとなぜわかるのか、座席の背もたれ越しに頭が見えるだけなのに、とおっしゃるのかね。頭で十分だよ、いうまでもないだろ、ハゲなの、ハゲ。きれいなスキンヘッドならさ、これまたちょっと話は違うんだけどね、その背広氏のハゲの直径は7センチくらいで、中途半端にとてもハゲだったさ。私はね、車窓から沿線の桜を眺めたかったのよ。阪急沿線には桜が多くて、通勤していた時代にも、この季節は車中花見が楽しみだった。通路側に座ったら、隣の誰かの横顔越しに窓の外を見ることになるから隣の誰かが誰であるかは重要なのである。そこしか空席がなかったら、私ももう年増やけん、ハゲでもスケベでも座ったが、ここに若い男の子がいるのになんで座らない理由があろうか。したがってハゲは却下。
若い男の子といっても特別にイケメンだったわけではない。座って車窓を見るふりしてその横顔を舐めるように(笑)眺めたが、好みにはほど遠い(ごめんね。あ、前の背広氏もごめんね。ハゲに罪はないのよ)。そして、驚くべきことと言うべきかどうかわからないが、彼(に限らないと思うけど)はほとんど微動だにせず、動かすのはスマホの画面を滑る指だけだった。ほんとにぴくりともせず、右手の指だけが、四角い薄っぺらい機械の上をすっすっと動くだけなのだ。彼は梅田のひとつ手前の十三で降りたが、「次は十三〜」のアナウンスが流れて初めて指の動きを止めて膝に置いていた鞄を持ち上げ、一度座り直し、上着を直し、立ち上がり私の膝の前をすり抜けるように去った。……のだがそれだけが私の見た彼の「人間らしい動作」で、「次は十三〜」があるまで、すっすっ……すっすっ……だけだったのである。これ、なかなかすごいことである。そんなに集中できるのね、スマホ操作に。
帰りの阪急電車の中では、向かい合った4人座席のひとつに座ったが、私以外の3人が全員、行きの電車の彼と同じことを始めた。全員を間断なく観察していたわけではないけれども、すっすっ……すっすっ……3人ともすっすっ……すっすっ……すっすっすっ……おおお、まったくすごい集中力。目がよってるよお嬢さん。ぴくりとも動かずに何かに熱中するそのエネルギー、ほかの何かにつかったほうがいいんじゃないの。
相変わらずラジオはマティニョン宮に到着した新首相のことばかり喋っている。ああ、ダニエル・オトゥイユの映画、観たくなったよ。すごく観たくなったよ。
Il était un petit navire... ― 2014/04/03 00:40:02
それからまもなく、ウイルス性の結膜炎になったらしくて右眼がまっ赤になり、上下両まぶたがパンパンに腫れて、眠っている間に目やにが噴出して目が開かないほどである……という散々な状態に慌てて眼科ヘ行き、心配ありませんよという優しいお言葉と点眼薬をもらって、最悪の状態から少し回復はした。したが、間もなくかゆみが治まらなくなり、これは結膜炎ではなく、花粉だとぴんときた。
まだ2月だというのに……。杉花粉しか飛んでいないはずなのに。
何年か前、花粉シーズンのまっただ中、耳鼻科医が処方してくれるアレルギー用の点眼薬が全然効かないので眼科に駆け込み、これを使っているんですけど効かないんです、とかゆみを治める目薬を頼んだのだが、私が差し出した点眼薬を見て眼科医は言った。「これが効かないのなら効く点眼薬はありません」
この年から、花粉シーズンの目のかゆみを治めることは諦めた。耳鼻科医もあれやこれやとさまざまな点眼薬を出して試させてくれるのだが、いずれも差した瞬間にひんやりして気持ちいいという以外の利点が見つからない。
こうしてブログ書いてる間も、目のかゆみのために私は涙が止まらないのである。
2月の終わりから薬を飲んでいた成果が少しばかりあったのか、3月は穏やかに過ごしたけれど、春分過ぎたあたりから目がつらいつらい。
この冬は雪と雨が多かったので、生乾きな感じの洗濯物を室内で乾かす日々が続いた。娘がいないので、彼女が宿題やらなんやらをひろげてあれこれの活動に使用していた居間が空いているのですっかり物干し場と化している。
2、3年前に隣家が家を建て替えたがそのおかげで向こうから見て北隣の我が家はまったく太陽の恩恵を受けなくなってしまった。きれいに晴れた日でも冬場は直射日光がない。建て替わってすぐのシーズンは物干しに並べている植木のいくつかが枯れてしまったほどだ。ったくどうしてくれるよ忌々しい。そんなわけで、とにかく天候に関係なく洗濯物は乾かないので部屋干し癖がついてしまった。やがて花粉が飛び始める。できるだけ花粉を浴びたり吸ったりしないように、屋外で干すのは御法度とした。
しかし、しかしですよ。今日は少し洗濯物を溜め込んだので大量の洗濯を敢行。……したはいいけど、部屋干し用の物干しに全部がかからない。しょうがないので屋外物干しにいくつかをかけた。問題はそれを取り込むときである。パンパンとはたいてから室内に持ち込むのはもちろんだが、はたいている最中に、はたかれた花粉が私に飛び移る。それが、きっといつまでも取れないのだ。
鼻水鼻づまりとは無縁だが、目のかゆみが甚だしい。花粉でかゆいのか、疲れてかゆいのか。たぶん、両方なのだろう。
しんどい。誰か私に目をちょうだい。
Moi non plus, je n'aime pas les jeux d'olympiques. ― 2014/04/05 21:53:27
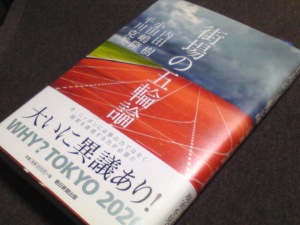
内田樹、小田嶋隆、平川克美共著
朝日新聞出版(2014年2月)
つねづね申し上げているように、東京オリンピックの招致には大反対だったわけである。東京だろうが大阪だろうが名古屋だろうが、大反対なのである。私はスポーツ観戦は好きだし、オリンピックで活躍するなんて、およそスポーツ好きな人間なら一度は夢見る頂点の栄誉だ。そのことだって否定しない。でも、オリンピックというイベントは全然好きではないのである。個別のゲームの観戦はしないでもない。昔から体操の演技は好きであった。ナディア・コマネチなんて私が男なら、今の表現でいえば「萌え」まくっていたであろう。新体操とかシンクロはあまり好きではなかったが、水泳の岩崎恭子ちゃんとか長崎宏子ちゃん(だったよね)には大いに期待したものだったし。でも、なんというか、個別に応援したい選手を目一杯応援する機会であるとか、よく観ておきたい種目をとびきり上等なプレイヤー達のプレイで観られる機会であるとか、普段は知らないスポーツについても観戦の機会があるとか、そういう個人的な趣味の範囲を満足させてくれる要素というのは、それぞれの競技のそれぞれの大会で得ればよいことであって、オリンピックというごたいそうなイベントにしてご提供いただかなくても困らないのである。こんな私のような者でもスポーツに打ち込んだ経験も勝利に酔った経験も怪我でプレイを断念した経験もあるので、思うような結果を出せなかった選手の気持ち、存分に力を出し切っても負けた選手の気持ち、てなものだって少しはわかるのである。目の前の勝負に全力を出し切ることだってたいへんなのに、背後でメダルの数をカウントされたり、国家の威信がどうのこうのと言われたり、経済的波及効果は何億円とか算盤はじかれたりして、そりゃいったいスポーツなのかいって話だよ。お国のために戦うなんて、もう第二次世界大戦の敗戦でこりごりじゃんか。お国のために戦うという言葉を使わなくても、ニッポンのみなさんの期待に応えますっていうのはつまり、同じことじゃんか。やめようよ、もう、そういうの、ってつくづく思うのよ。気持ち悪いって。というわけで、なぜ東京にオリンピックが来て欲しくなかったかと言うと、このイベント、ひたすら気持ち悪いからである。いえ私はね、前の東京オリンピックの年に生まれたざんすよ。自分の年を数えたり、生まれた頃の時代を想像するのにこれはとても便利だよ。1964年という年、当時は冬季五輪も同じ年に開催されていたからどっかで冬のオリンピックやってたんだよね、それと阪神がリーグ優勝してるのよウチのオヤジは大喜びだったらしいよ私が虎の優勝を呼んだって(笑)。海外旅行もできるようになったんだってこの年から(それまでできなかったってのが信じられないんだけどね、そんな国そんな時代だったんだよ)。敗戦後約20年経って、やっと顔を上げて世界に向けて「こんにちは、ニッポンです」っていえるようになった頃だったんだ。オリンピックはそんなニッポンにキラキラのメダルをくれたんだ。だから開会式の10月10日を体育の日として日本人の記憶に刷り込みたいと思ったんだろうに、どっかのアホがハッピーマンデーとか言って10月10日を忘却の彼方に押しやってしまった。その頃からじゃないか、オリンピックが金の亡者たちのための金儲けのためだけのイベントに成り下がったのは。2020年。きっと、それぞれにとって忘れ難いさまざまな出来事に彩られることになるであろう2020年、その一年の中でひときわ輝く東京オリンピック。ほんとうにそうなればいい。そのとき、日本と日本人が、心の底から世界の人々を迎え入れることができ、心の底から国際交流と親善のために選手と関係者と観戦に来る人々をもてなすことができ、心の底から世界の人々と笑い、語らうことができ、豊かな自然を湛える美しい国土と清廉な大和魂を印象づけることができればいい。何の憂いもなく、心に疚しいことの微塵もなく、後ろめたい気分などかけらもない、晴れ晴れとした気持ちでオリンピックを開催できるなら、いい。
しかし、そんなこてゃーありゃーせんがよー、と思う人たちが、なぜそう思うのかを好きなだけくっちゃべっているのが本書である。2013年10月に行われた鼎談を収録したものだ。
ふだんウチダのブログや書き物を読んでいる私には、目新しい内容ではないことはわかっていた。それでもこの本を買ったのは、やはりオリンピック招致キャンペーンが余りにも気持ち悪くそらぞらしく、無邪気に一生懸命になっている人たちには悪いけど安倍や猪瀬が目立ちたいだけのパフォーマンスにいいようにつきあわされているようにしか見えなくて、吐きそうになるくらい嫌だった、だから、この本を読めば、「そうよ、そのとおりよねウチダ」「同感だわウチダ」「あなたって私の分身のようだわウチダ」「私の気持ち全部知ってるのねウチダ」「あなた以外に私を理解してくれる人なんかいないわウチダ」……とこのようにウチダLOVE全開になれて鬱々とした日々のモヤモヤをすっ飛ばせるかと思ったのである。
しかし。
たしかに内容は、「そうよ、そのとおりよね」「同感だわ」の連続なんだけど、うなずく相手がウチダではないのである。小田嶋や平川なのである。この本さ、わたし、頼んでもいないのにAmazon.co.jpから内田樹の新刊が出ますよってメール来たのよ、それって内田樹が著者ってことでしょ。でもよく見たら共著で、しかも鼎談だって。どうしようかなってかなり迷ったけれどもやはり先述のような理由から買うことを決め、予約を入れたのである。こんなふうにまだ出てもいない本を予約して買うなんて、チョー珍しいことなのだ、わたしの場合。いちおう期待したのである、中身に。なのに届いた本を読むと(数時間で読んでしまった)、小田嶋と平川ばかりが喋っている。ウチダ、セリフ少なっ。これ、そう思うの私だけかな? なんかさ、すっごく、めっさめさ、騙された気分(笑)。
しかし、まあ、3人が3人とも今回の五輪招致騒ぎを苦々しく思い、招致が決まって憂鬱になっている人々なので、主張は一緒で、同じ考えをもつ者にとって読みやすくひたすら相づちを打ちながら読み進める1冊には違いない。自分のモヤモヤを誰でもいいから言葉にしてくれないかなと思ったらこれを読めばきれいに言葉になっていて、一時的にはスッキリする。しかしその「モヤモヤ」は著者たちももっているので、けっきょくこのモヤモヤなんとかしてくれよどうにかならんかい、という感じで鼎談が終わるので、モヤモヤの根本原因の解決には、もちろんならない。ならないが、オリンピックなんかやめようぜと思う人が少なくとも自分を含めて4人居ることがわかったんだし、ならばもう少しいるだろうということで、希望をもつこともできる。
何の希望?
東京オリンピックの中止。
……無理か……。
何の希望?
まともな思考の日本人も少しは存在すること。
ほんまやで、たのむわ。
Il neige... ― 2014/04/07 22:27:29

工藤信彦著
岩波ジュニア新書(1983年)
娘からぽつりぽつりと来るメールを読むたびに、ああほんまにお前は作文コンクールなるもので三度も賞を獲ったのか、ほんまにお前は出願時の自己PR書提出と試験日の小論文とで高校入試を突破できたのか、それって全部何かの間違いだったんじゃないのか、といちいち思う。それほどまでにヤツの文章には誤字誤変換が多く、口語と文語の区別ができてなくて、主従がねじれて、文章の主体が不明で、議論は支離滅裂である。今始まったことではないし、我が娘に限った話ではない。そんなことから、2、3年前だが、ここはひとつ青少年の未来のために小論文塾をやるぞという話が私の周囲で一度盛り上がったのだが、塾用のサイトをつくるぞ!と言っていた人の体調がすぐれず立ち消えになった。だがもし始めていたらどうだったか。どんな形で始めたにせよ、今の子どもたちの手の施しようのないほどの「書けなさ」に愕然とするばかりだったんじゃなかろうか。書けないだけではない。きちんと話せない。ひと昔前の日本人と違って今の子どもたちは人前で話すことを怖がらないが、それときれいに話せるということとは別問題である。ふだんラジオを聴いているのでよくわかる。若いアナウンサーたちは、アナウンサーを名乗るための訓練を受けている人たちである。美しい声の持ち主たちである。発音もよい。明朗である。しかし、話しかたは美しくない。ニュースを読んでいる時を除いて。はっきりと言葉を発音するが、例外なく「ら抜き」であり、必要以上に語尾が伸びる。とにかくなんでもどんな時でも最後に「で」をくっつけて、「それでぇ〜」「○○でぇ〜」「△△になったんでぇ〜」「なのでえー、それは違うということでぇー」……。
破綻しているのは娘の文章だけではない。日本全体の話し言葉と書き言葉だ。つまり日本語の遣われかたそのものが破綻している。
私たちの先行世代が育てて世に出した駆け出し社会人たちがこのていたらくであるということは、先行世代の日本語もアヤシイものであり、こうなると、私たちが育てて世に出さんとしている青少年たちはもっとアヤシく、私たち=青少年の親たちの日本語もアヤシイ。アヤシイもんたちがアヤシイもんたちを育ててアヤシさの二乗三乗にしたらアヤシイがふつうになりアヤシイのスペリオールが出現しさらにアヤシイものを求める世となってしまうだろう。アヤシイ日本語に歯止めが効かなくなる。
そんなところで、こそこそと小論文塾サイトを開いても、焼け石に水。
そうした絶望感に苛まれていたある日、仕事帰りに立ち寄った本屋で目に留まったのが本書である。
表紙がいい。
HBの鉛筆がある。万年筆もある。
著者の工藤先生は1930年生まれの国語の先生だ。
本書はとても真面目で地に足着いた、綴り方の学習書である。
日記を書くことの楽しさと、思わぬ効用を語る。
手紙を書く時の礼儀作法を説く。
感想文を書く時の、対象作品に対する心得を、丁寧に述べる。
奇をてらったテクニックや、必ず試験に出るテーマだとか、これを知っておけば試験はクリアできるとか、そんなことは1行も書いてなくて、文章を書くという行為のシンプルなよさ、楽しさを知らせたいという情熱にあふれている。
《みなさんは、文章を書くということを、どのように考えていますか。心のなかにもやもやと存在しているものを、ことばで書き表わしてみると、自分の感じたり考えたりしていることが、はっきりと見えてきて、それによって自分をあらためて見直すということがあるでしょう。文章には、心で感じたり考えたりしていることを、整理する働きがあります。
また、文章を通して自分が考えたことを相手に伝え、相手からもまた考えを示されて、お互いに心を通じあって生きてゆくことができます。これは、人生において文章のもつ重要な役割です。》(2ページ)
冒頭のこの数行で、この先生がどれほど日本語と日本語で書くことを愛しているかがわかるというものである。なんと、文章を書くということは単純で素直な営みなのであろうか。こんなに単純で素直なことならなぜに私たちは文章を書くことにこれほど四苦八苦するのか。
《ことばは心を裏切ると、よく言います。感じたことや考えたことをことばで表現してみると、どこか気持ちとくいちがってくるのです。ことばはなかなか心を正直に伝えてくれません。ことばを見出せないもどかしさがペンを止めてしまいます。》(3ページ)
「ことばを見出せないもどかしさがペンを止めてしま」うだなんて、ああ、工藤先生、あなたは詩人ね。書けずに苦しみ、んんががががコンチクショウ、と叫ぶさまを、「ことばを見出せないもどかしさがペンを止めてしま」う、とこれほどまでに美しい表現で言い放った人がいたか? しかも、べつに美辞麗句を連ねているわけではない。
しかし私たちが日常ぶち当たっているのはまさしく「ことばを見出せないもどかしさ」なのである。
感想文の章で工藤先生は三好達治の詩を引いて、こう述べる。
《詩の読み方には、その作品を読む人のさまざまな読み方があっていいでしょう。この詩で注目したいところは、〈雪ふりつむ〉という表現です。
みなさんの知っている雪はどのように降りますか。遠い異国となってしまったサハリン(旧南樺太)生まれの私の記憶の中には、雪は降らせるものではなく、降りゆくものでしかありません。(中略)雪の降り方が一様でないように、人びとの雪の感覚もまた、多彩なのです。したがって、いくつかの感じ方があるのではなく、一人の人間には一つの感じ方しかできないことを知ることが、大切なのです。》(113〜114ページ)
日本語は、雨や雪、風や陽射しなど天候や自然現象の表現に富むとはよくいわれるところだ。とはいえ、数多の表現のあることと、ある人間の感じかたのありようとはかかわりがない。降る雪をみてどう感じるかは雪を見る本人固有のものだ。
三好達治が「ふりつむ」と表現した雪は、三好が見た雪だ。三好の見た雪を想像する。もはや降る雪を三好と同じ時間空間では見られない以上、想像するしかない。ここで想像力が問われるが、「一人の人間には一つの感じ方しかできない」。とすれば、「ふりつむ」ってあんなんかな、こんなんかなと思い描くのではなくて、ただ三好が見た雪を三好になって心眼で見る。
そうすると、この詩を対象にした感想文なんぞ、シンプルにシャッと書き上がるであろう。
だが、けっして、近道をガイドする学習書ではない。そうではなくて、きちんと射るべき的を射ること、「コア」を見誤らないこと、回り道になってもたどるべき場所をたどること。それらのことは工藤先生も力説しておられる。
それにしても、工藤先生の文章は「の」がきれいだ。「の」を美しく使うこと。現在失われている用法のうち、いちばん忘れて欲しくないのが「の」である。どの「の」のことか、わかる?
Donc, c'est pour ça... ― 2014/04/10 09:03:25
武田百合子 著 武田花 写真
ちくま文庫(1993年)
娘の友達の進学祝いに、ノートやらペンやらを揃えながら、ふと、小さな本はどうだろうと思って考えた。小さな本、というのはサイズのことではなく、もらったほうがべつに重く感じないで済む、という意味だ。その子はいずれ海外留学も計画しているので、なんか「世界に羽ばたく」感全開!の本がいいのかなと思ったけど、ではなくて武田百合子のエッセイの文庫にした。
武田泰淳のある小説が気に入って、その流れで武田百合子のことを知った。読みたい読みたいと思いながら後回しにしていて、いまさらながらなんだがようやく去年、2冊の文庫を入手し、しみじみ読んだ。『ことばの食卓』と『遊覧日記』だ。
私は、文章書きの例に漏れず須賀敦子の文章が好きで(みんな好きだよね?)、こんなふうにしっとり書けたらいいなあと読んでは溜め息をついている。
ある時、装幀のたたずまいがいたく気に入ったある随筆集を衝動買いした。外国暮らしの長い日本女性の、その滞在先でのあれこれを綴ったものだった。きれいな文章なんだけど、「須賀敦子さん意識しまくり」が見事に透けて見えてしまう。いや、これは私が須賀ファンなのでそのように読んでしまうのかもしれない。すぐれたエッセイに与えられるそれなりの文学賞を受賞されている人なので、私ごときが難癖つけるなんておこがましいけど、そしてなによりご本人は須賀敦子に似せてる気なんて微塵もないかもしれないのだけど、でも、この本には須賀敦子の文章にあるような「かの地の空気」はなくて、須賀敦子っぽい文体と構成は、ある。とそんなわけで、衝動買いしたけど、期待はずれでがっかりした本の巻、だった。
武田百合子のエッセイは、とても、いい。
文法や、文章を書く上でのルールとか、細かいことで突っ込める箇所は、実はたくさんあるけれども、とてもきれいな日本語である。須賀敦子のように異国の空気をそのまま目の前に運んでくれるようなことはないけれど、武田百合子の描写はストレートで、ふだんどうでもいいような、見逃してしまいそうな、日常の断片を読者の代わりに観察してつぶさに綴りあげる。それを読んで読者は、まるで対象を武田と同じように見ている気持ちになる、のではない。むしろ、そんなふうに見て書いてしまう武田百合子というご婦人の、ものを見る目に感心してしまう。人って怖いな、と思うのだ。
娘の友達には、手元にある2冊のエッセイ集を読み比べて、『ことばの食卓』のほうを贈ることにした。いや、自分が読んだやつじゃなくて、新たに買いましたけど。『ことばの食卓』のほうが、話題がより平坦で、だからこそひとつひとつの言葉がきらめいて見える。ぞんざいな言葉遣いをしがちな若者には、また、英語至上主義に踊らされて、目が外ばかりに向きがちな若者にはこちらのほうがいいと思った。
で、『遊覧日記』である。
「遊覧」つまり物見遊山日記である。いいなあ。羨ましー。
《夫が他界し、娘は成人し、独りものに戻った私は、会社づとめをしないつれづれに、ゴム底の靴を履き、行きたい場所へ出かけて行く。》(10ページ)
羨ましいでしょ?(笑)
浅草がお気に入りだったそうで、浅草へのおでかけ記が冒頭から3編続く。私には浅草へは若い頃一度、半日ほど歩いた経験しかない。その記憶の浅草も相当古いが、武田百合子の描く当時の浅草も、また昔のものだ。だが、浅草という土地のイメージが醸し出す何かが、エッセイを極端にノスタルジックなものにはしていない。武田の、風景や人物を描写する筆致におかしみがあって、対象はなんであれ、自分もこんなふうに描き出したいと思うのだ。
《女はワニ皮の大きなハンドバッグを、しわ深い膨らんだ指で大切そうにいじりながら、池を見ている。紫色の光るブラウスと豹の模様のビロードのスーツに、肥り返った体を押しこみ、ひすい色の耳輪をぶら下げている。厚く塗った白粉と口紅の横向きの顔は、六十を過ぎていそうだ。それでも元気そうだ。立派だ。年季の入ったストリッパーかもしれない。》(16ページ)
《いやに彫りが深くて色白の、元美貌、そのため却って、お金のなさそうな人にみえる老紳士》(34ページ)
上野や富士山麓の章があり、京都の章もある。いろいろなところヘ行って、こんなふうに旅や散策を綴れるっていいよなと思う。しかし、最後の章「あの頃」を読み、深く反省する。
武田百合子が晩年どのように、好きに、気ままに生きたとしても、誰に何を言われる筋合いはないというものだ。「あの頃」を生きた人であるからには、「あの頃」以降に生まれた者は一生逆立ちしてもかなわない。
「あの頃」とは終戦間もない頃。焼け出されて弟とその日暮らしをしていた頃。進駐軍のいいなりになるしか生きる術のなかった日本と日本人の頃。
だが、「あの頃」の章ですら、おかしみに満ちていて、人間、こうでなくちゃ、物書き、こうでなくちゃ、とやはりしみじみ読むのである。
Et vous, vous pensez à quoi, Victor? ― 2014/04/13 09:55:27


Que c'est beau! Tout est beau! ― 2014/04/14 21:04:22



Ce que je voulais faire ― 2014/04/18 00:29:33












On a toujours une conscience tourmentée, cela ne dépends pas du tout de l'âge. ― 2014/04/25 00:16:56
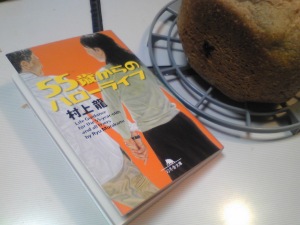
村上龍著
幻冬舎文庫(2014年4月)
行きつけの書店(けっしていちばん好きな書店ではないが)で前にもらった金券100円分があったので、文庫本でも買おうと立ち寄った。その書店のレイアウトは、会社勤めの若い男女を意識しているということのよく伝わる、わかりやすい配架になっている。こっち向いたら政治経済社会、そっち向いたら京都本著名人本スピリチュアル系心に残る言葉系。私はいつも、出入り口付近のその「参道」はすっと抜けて、実用書(旅行、料理、手芸)の壁または思想・哲学・文学系書架を眺める。買うことはほとんどない。誰が、どんなことを、どんな装幀の本の中で述べているのか、その概略をつまめたらそれでいい。いや、ほんとうは買いたいのだ、目についた本を全部。でも、我が家は私の蔵書のせいで敷居も鴨居もしなって傾き建具を引くことができないありさまゆえ、これ以上本を増やすわけにはいかない。と、けなげにもいつも諦めているのである。涙をのんでいるのである。……というのは、ほとんど嘘である。たしかに欲しい本全部は買っていない。全部は買っていないが、さんざん吟味した挙句、これだけ買うわごめんね我が家、とつぶやきながら究極の一冊を手に、それでも書架の前にしばし立ちすくみさんざん逡巡する。いったいどのくらい時間を費やすつもりなんだ早く決心してレジへ行け、と己に言い聞かせてやっとキャッシャーに足が向く。……というのはごく稀なケースである。私はたいてい時間に追われているので、そんなに贅沢に時間を費やして本を買うかどうかを迷い悩み続ける余裕はないのだ。したがって、どうしよっかなエエイ買うてまえ〜と2、3冊つかんでちゃっちゃとレジに並んでいる、というのがほとんどのケースなのである。これ以上本を増やすわけにいかないと自分に言い聞かせるようになってからもう幾年も経っている。その間、言い聞かせているのはいったい誰なのよと自問するのも時間の無駄とばかりにおおおっこれはっよし買うでえっと衝動買いに近いというか衝動買いばかりで本を買うので、本は増える。衝動買いするのは装幀の美しい本が多い。そして中身はチョー軽薄orチョー冗長orチョー説教臭いというわけで結論チョー期待外れ、だったりするので、男とおんなじだ、なんてあたしは本を見る目がないのだろう、と打ちひしがれたりする間もなく増えた本に唖然として溜め息をついている。ここ何年もの間にたしかに少なくない本を古本屋に売ったけれども、やっぱ本は増えている。私はけっして蔵書家などではない。でも我が家のキャパは超えている。しかしそうした厳しい現実から逃避するのは大得意である。で、今回のように、よく空が晴れて陽光麗しく、財布の中には金券、なんて日は、我が家の実情を忘れてルンルンと本屋へ向かうのだ。
最近の文庫は漫画単行本(コミックス)みたいな表紙が増えて、子ども向けアニメのノベライズなのかライトノベルなのかエロ漫画なのか、いや文学賞受賞作家のシリアスな小説だった、みたいなケースが多々ある。紛らわしい……。いくら文庫でももうちょっと装幀、真面目に考えようよ。そんなわけで、私は文庫に限っていえば衝動買いはしない。美しい装幀なんかないからだ。文庫の場合は、図書館で読んだ単行本にいたく感動して忘れられず、どうしても欲しいけどあの分厚い単行本は高いよな……と思っていたら文庫になっていた!よしゴーバイ!!みたいな時に限るのである。……というのは今回の場合まったく当てはまらなかった。文庫の書架の前へ来て、ケバい表紙たちに辟易しながら、なんやこれ、なんやこれ、もうちょっとさ、しゅっとして気の利いた表紙はないのんかい、持ち歩けへんやんこんなん、と心の中で悪態をつきながら、やっぱやめとこと通過しかけて、ある本に目が釘付けになった。それが本書だ。
55歳のハローワークやて、ぷぷぷっ、今のあたしにぴったりやん(私は目下プー子〈失業女〉であるから)、さすがはリュウね♪、あら、これ小林薫ちゃう? そうちゃう? そうやん、小林薫でドラマ化って帯ついてるやん、そうなんふーんテレビは見いひんけど小林薫やて、ええわあ、と、私はそのまま考えを反芻することなく、平積みになっていた本書をガッとつかんで、文庫を生まれて初めてと言っていいだろう、衝動買いした。
表紙はイラストで、熟年男女が手をつないでいる後ろ姿だが、斜め後ろから見える男の目元が小林薫だった。私は小林薫を激しく好きである。状況劇場に所属していた頃からのファンである。おっさんになってもほんまにええ男である。
平日の昼間のせいかレジカウンターにはキャッシャーがあまりいなくて、しばし列の後ろで待った。そのあいだに、表紙、そして帯をよく眺めると、55歳のハローワークじゃなくて『55歳からのハローライフ』なのだった。ワークじゃなくてライフ(笑)。ワイフでもなくてライフ。なんやねん、それ。あ、そうか。再就職の話ではなくて、人生の再出発の話なのだ。
子どもが成人して一段落した時にふと配偶者を眺め、「嫌」だという思いが募って離婚に踏み切る。定年前に会社をリストラされるが再就職の望みは薄い。早期退職して夫婦で旅行したかったのに妻は乗り気でなく。ある日ふと出会った女、熟年を迎えて生まれて初めて女にときめいたのに。とか、どれもこれも、身につまされる(笑)。
中編小説が5編収録されていて、どれも、読ませる。さすがはリュウね。本書には、いつもうじゃうじゃ出てくる変態オヤジは出てこないが(ひとりだけ出てくるが主要人物でない)、そのぶん、まともでまっとうな一小市民の人生にこれほどまでに苦悩と困難があるのか、でも、そうだよな、みんなそうだよなと、うんうんわかるわかると読み進むのである。読み進むが、結末まで来て、なんだか説教臭い終わりかたに、釈然としない。村上龍は述べている。この小説の主題は、中高年にエールを送ることだ。しょぼくれてないで、顔をあげて前を向いて、まだまだ続く未来への道を歩こう。そう元気づけるために書いたという。主人公たちはみな作家と同世代で、作家は非常なシンパシイを感じつつ書き進み、読者がよしオレもアタシも頑張ろっと前向きになってくれたらいいと願った、みたいなことを述べている。
ま、それはいいけど。
最後の5行くらいで、妙に主人公が希望に満ちたり、再出発を誓ったり。つまりは、いい方向へ向かって終わるのだが、中編小説集でどれもそういうふうに終わられると、ちょっとつまらない。この中編小説集の趣旨が最初から55歳へのエールだからしょうがないと言えばしょうがないのだけど、救いようのない話がひとつぐらいあってもいいのに(笑)と思うのは私だけだろうか。
思えば村上龍の作品は、変態オヤジがよく出てくるとはいえ、どちらかというと未来に希望のもてる終わりかたをするものが、もともと多いかもしれない。ここで引き合いに出すのはあまりに唐突だが、村上春樹はラストで読者を突き放して置いてきぼりにするのが常套手段だ。けったいな話が、それで妙にリアリティに満ちる。
本書の物語はいずれもたいへんよくある話で、自分の身に起こってもおかしくはなく、だからそれだけに、さまざまなエピソードののちに、主人公がわかったふうなことをつぶやいて終わるかたちをとっていることで、リアリティが減じている。残念。物語の起伏や挿話の運ばれかたも隙がなく、とても面白い。小説ってこう書くのね、の見本みたいである。でも、ひとつぐらいは主人公とその相方が奈落の底に落ちる話でもよかったのに(しつこい?)。
《うんと遠くにいる相手のところまで行って大切な何かを伝えるって、それだけですごい価値がある気がする。》(63ページ「結婚相談所」)
Avril ― 2014/04/30 23:37:49







